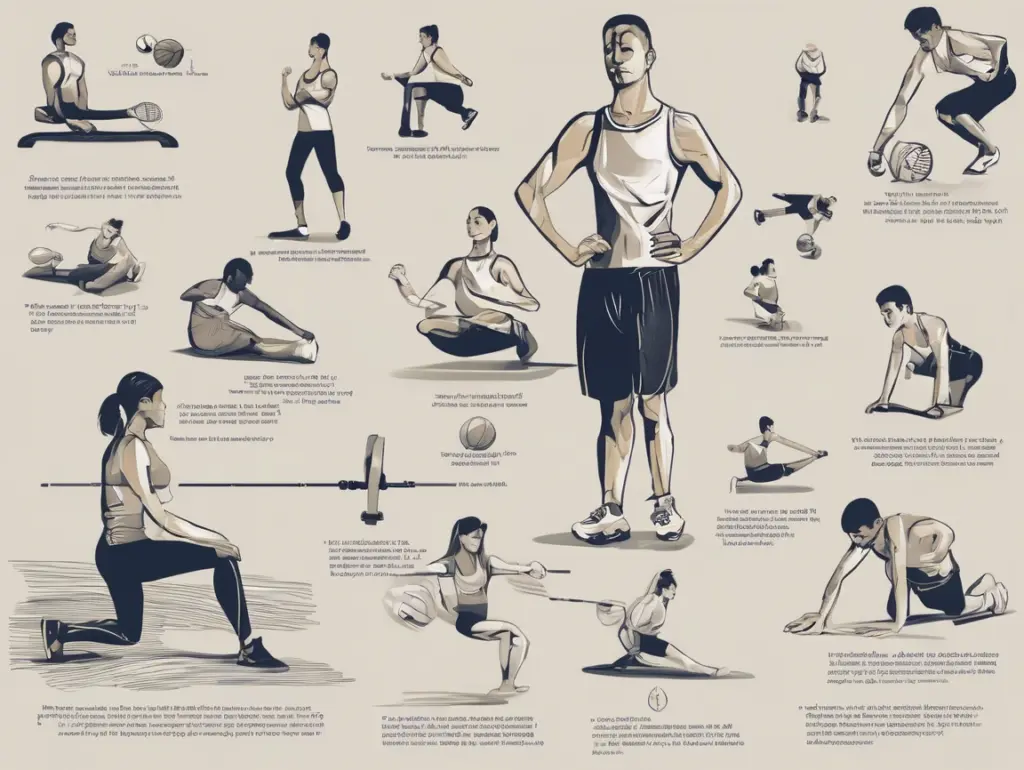
練習においては、「観察」が不可欠です。自分の体や心を観察することで、何が足りないかを理解し、より良い成果を得ることができます。自己観察には謙虚さが求められ、自分の心の状態を見極めることが成長へのカギです。
これを読まれている方は、熱心に練習に取り組まれている方が多いでしょう。しかし、熱心に取り組んでいても、なかなか答えが見つからなかったり、うまくできるようにならない、という方も多いと思います。実は、「こうすればできる」という「答え」を探すよりももっと手前に考えなければいけないこと、理解しなければいけないことがあり、そこで必要となるのが「観察」です。
運動をする、ということは、あたりまえのことですが、「自分の体」を動かすことです。それは誰の体でもなく、自分だけの体であり、自分の体を動かすことができるのは自分だけです。 例えば、「力を抜く」というアドバイスを例にしてみましょう。あなたにとっての「力を抜く」と私にとっての「力を抜く」は同じでしょうか。そして、プロのアスリートにとっての「力を抜く」は同じでしょうか。それは、それぞれの中での「力を抜く」があるはずです。私の中での「力を抜く」とあなたの中での「力を抜く」、プロの選手にとっての「力を抜く」は、おそらく違うものでしょう。
あなたが何かを変えたいと思い、「答え」を求めているとしましょう。例えば、コーチが、先輩が、先生が、動画の中に、「答え」を見つけたと思っても、それはその人の中で生まれた「答え」であって、それは私の中にある「答え」とは違うのです。ですので、その人の体で感じて紡がれた「答え」を受け取ったとしても、受け取った瞬間にその「答え」は自分の中の「答え」に変換されて受け取ることしかできません。
この壁を乗り越えるのが、「観察」です。自分の体や心を「観察」することで、今の自分を客観的に、正確に、理解していくことができます。そして、今の自分が理解できていくと、自分の足りていないところ、改善すべき点が具体的に体感できていくので、「答え」を自分の体に、心に落とし込んでいくことができるのです。
例えば「力を抜く」という例で考えてみると、「力を抜く」という「答え」を受け取ったとしても、今の自分の身体がどうなっているのか、力が入っているのか、どこに力が入っているのか、という理解がなければ、力をどう抜いていいのか、果たして力が抜けているのかいないのか、もわかりません。今の自分の身体がどうなっているのかが観察し、どこに力が入っている、もしくは力が入っていそうか、と理解できた時に、「力を抜くことができていないのかもしれない」と頭と心と体のすべてで気づくことができ、そこに「答え」が入ってくることによって、その「答え」を自分の体に落とし込み、自分の中での「力を抜く」にしていくことができるのです。
観察するー身体を観察する
テーマや改善点を明確にして練習に臨む際には、何かしら動きに変化を求めて取り組みます。ですので、自分の身体がどのように動いているのか、どのように力が入っているのか、どのような状態にあるのか、といったことを観察するようにしてください。観察を行わなければ、実際に変化が生まれているのか、いないのか、がわからないまま、ただボールを打つ無駄な時間を過ごすことになってしまいます。
観察をする際には、謙虚に自分の体に耳を澄ませて聞きましょう。例えば、選手に「どこの力で動かしていると感じますか」と聞いた時、時折答えとして返ってくるのは、「腰の回転」や「足の力」といった、誰かに言われたアドバイスや、どこかに書かれていた知識から出たであろう答えを聞くことがあります。
これは、「どこの力で動かしていると感じているか」という問いに対する答えではなく、「どこの力で動かすべきか」という問いに対する答えです。そうではなく、ここで問うべきなのは、「自分がどこの力で動かしていると感じているか」を観察することなので、むしろ「わかりません。」と答えたほうが正解であり、「わからない」ということがわかれば、「どうしたら『どこの力で動かしていると感じれるか』」という、自分の体への理解へのスタート地点煮立つことができるのですが、どこかで書かれていた知識を答えている限り、そのスタート地点に立つことができないので、自分の体がどうなっているかを理解することができないのです。
自分の体を観察し、自分の体の力の状態を感じることで、今取り組んでいることが正しいのか、変化が生まれているのか、あるいは何か取り組み方を工夫したほうがよいのか、ということが明らかになっていきます。
観察するー心を観察する
心身一如という言葉があります。肉体と精神は一体のもので、分けることができないものであることを表しています。様々な選手の動きを見ていると、この言葉が表す意味がよくわかります。例えば意志が強い選手は堂々とした風貌ですし、弱気な選手は少し縮こまっている様子を見せます。そして打ち方にも心のあり方は表れてくるもので、小手先でごまかそうとする選手はそういう動きになりますし、思い切りの良い選手はそういう動きを見せます。つまり、動きを変えていく、ということは、自分の心がどのようなあり方なのかを見つめる、ということでもあります。
また、試合を通して「メンタル」が課題だと感じる選手は多いと思います。練習と試合で違ってしまう、練習通りの自分が出せれば試合でも結果が違うのに、と思う方もいらっしゃると思います。ですが、少し振り返ってみてください。練習の中で、あなたの課題に取り組む時に、例えば焦って早く結果を出そうとしてしまったり、小手先で調整してとりつくろうことを考えたり、そんな自分はいませんでしょうか。たしかに試合のときには、自分の心のありようがはっきりと表れますが、その自分は試合の時にわかりやすく表れているだけであって、普段からきちんと自分の中に存在しています。
たとえば課題に取り組む中で、心のあり方が影響している部分がないか、観察をしてみましょう。あなたの動きを改善するにあたって、その課題となる動きに心が影響を与えているかもしれませんし、練習や課題に取り組む時にその取り組み方に心が影響を与えているかもしれません。
ある選手は、真面目に取り組んではいるのですが、なかなか結果が出ない選手でした。その選手は、課題や意識すべきことを頭では理解して、一見まじめに取り組んでいましたが、いざ練習になると課題に意識が向かず、改善が続かないことが起きていました。本人と話をする中で、「できていない自分を許せない」という心があり、それが自分の課題や改善点から目を背ける原因になっていた、というようなケースがあります。
また、道具との関係についての紹介でも書きましたが、「自分が道具をコントロールする、制御する」と考えると、体に力が入り、力みで道具を支配しようとしますが、「道具の力を発揮するために自分が何ができるか」と、道具のために自分に何ができるか、という心で捉えられると、体の力は抜け、スムーズで自然な動きができるようになっていきます。
こうした心のあり方は、性格だ、と捉えたり、無意識でなってしまうものであって変えられないものである、と思うかもしれません。ですが、よくよく観察して向き合うと、無意識のうちにどのようなことを考えているか、少しずつ明らかになってきます。自分だけのノートを作り、そのノートに書き出してみることはオススメです。やりたくない自分、めんどくさい自分、焦っている自分、かっこつけたい自分、どんな自分でも、そのノートには思ったままを表してみてください。
この時に、「こういう自分でありたい」「自分はこういう人間のはずだ」という思いが強いと、なかなか心のあり方は見えてきません。このような思いが強いと、「やりたくない自分ではダメだ」と封じ込めてしまい、「やりたくない自分」がなぜやりたくないと思っているのか、と問うことができません。でもあなたの中にはたしかに「やりたくない自分」が存在していて、その自分が存在することを認めることで初めて「やりたくない自分」が「やれるようになる」ための方法を見つけていくことができます。
【チェックポイント】
