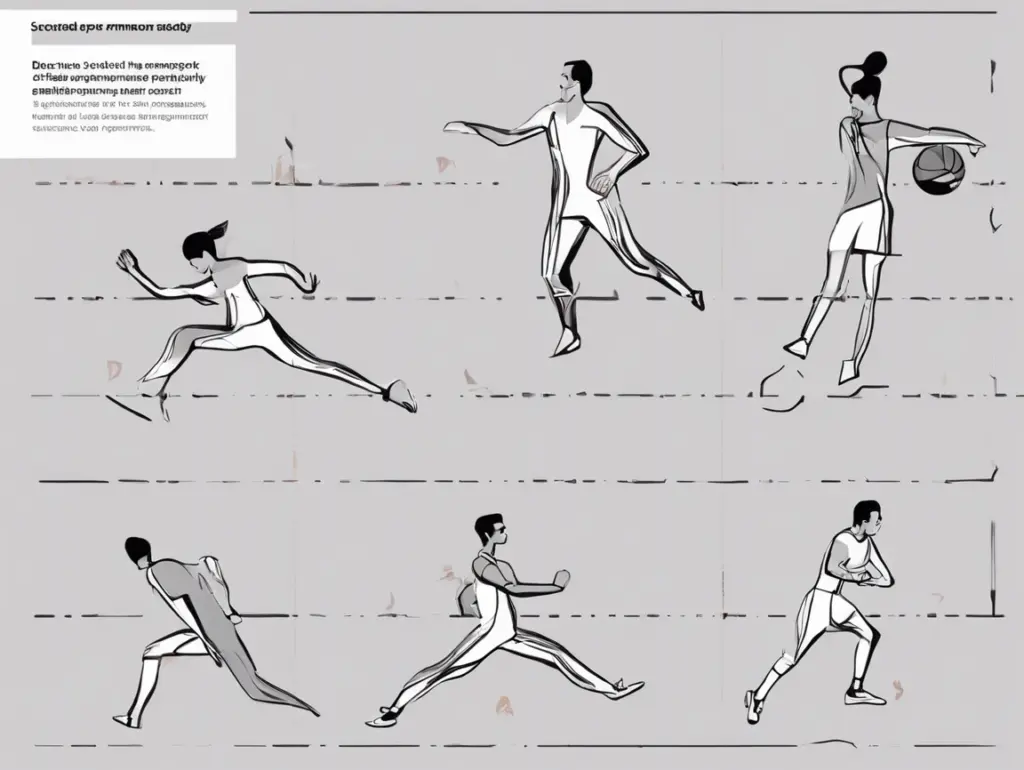
運動やスポーツに臨む際、多くの人が「力が抜けない」「効率的な体の使い方ができない」「安定しない」「なかなか技術が改善しない」といった悩みを抱えることがあるでしょう。果たして、これらの課題はどこから生じ、そしてどうしたら改善するのでしょうか?たくさんの努力と時間を費やしても、努力の方向性が異なっていたら、改善がなかなかされないかもしれません。今回は、体の使い方やフォーム、そしてスポーツ全般の技術について考えたいと思います。
フォームの再考: 形ではなく力の使い方に目を向ける
多くの場合、スポーツの技術を改善しようとする時「フォーム」や「形」に対してアプローチしてしまうと思います。
例えば、「フォロースルーはこうする」「右腕はこの位置に」「足が開かないように」「開きをおさえる」といったアドバイスを誰しもが受けたことがあるでしょう。
しかし、ここで少し立ち止まって考えてみましょう。体の形やフォーム、というのは、あなたがどのように力を使い、どのように力を抜いて、体を使っているか、という、力の使い方の結果として表れているものでしかありません。フォームは、あくまで体がどのように力を使っているかの外見的な結果なのです。このポイントを見失ったままフォームだけを変更しようとしても、力の使い方が変わっていなければ根本的な解決策にはならず、変化が生まれません。
逆に力の使い方を意識して修正することで、フォームは自然に適切なものに変わっていきます。
力の使い方に影響を与える思考と感覚
ここで難しいのは、力の使い方を理解し、教わることの難しさです。
例えば「力を抜きましょう」と言われても、力を抜く感覚が共有できなければ、本当に力が抜けているのかどうかが理解できない、ということです。例えば、あなたの「力を抜く」と、トップ選手の「力を抜く」はきっと違うものでしょう。実際に体感できて初めて理解ができることになります。
では、どうしたらよいのでしょう。
体の仕組みを考えた時に、実際の筋肉の動きや力をどれだけ加えるか、は、脳が司令を出しています。つまり、「どう力を発揮するか」という考えが、筋肉の動きや力の強さに影響を与えるのです。自分の中にある「良い」と思う体の使い方を、体に信号として伝えます。この信号が身体に伝わり、筋肉はそれに反応し、動きが形成されていきます。
ということは、体の使い方には、体をどう使うか、という考え方や捉え方が影響している、と考えることができます。
ある論文では、性格や考え方が動きやフォームに影響している、という指摘もされているます。「力をどう発揮するか」という考え方や捉え方が実際の信号として、筋肉に伝えられているのです。
Mind to move: Differences in running biomechanics between sensing and intuition shod runners
ということは、自分がどのような考え方をしているか、という部分を理解し、そこに変化が生まれたら、体の動きや力の使い方にも自然に変化が生まれてくる、ということが言えます。
道具や体をコントロールする?
では、動作に変化が生まれるような考え方や捉え方というのはどういうものでしょうか。
ここで、藤田一照僧侶が書かれた現代「只管打坐」講義から、智慧をお借りしたいと思います。ここでは、坐禅に取り組む際の、「姿勢」や「呼吸」に対して取り組む際のことについて、検討されています。
たとえば、わたしがみなさんに向かって「姿勢を意識してください」と言えば、たいていの人は足の位置を変えたり、背中を伸ばしたりしてすぐさま姿勢を「正す」ような動きをするだろう。『動いてください」と言ったわけではないのに妙に動いてしまうのである。つまりここでは「意識する=コントロールする」になっているのだ。自分が今どのような状態であるかを感じる前に、自分が「良い」と思い込んでいる状態に変えようとコントロールする。そういう根深い習性をわれわれは持っているようだ。
私達は、何かに取り組む際に、何かを変え、制御したり、コントロールしようとする傾向がありますし、そのように教わってきた方も多いと思います。フォームや動きを変えようとするときは、「なにか動きを変える」「動きを加える」という取り組みを行い、何かをしなければ居心地が悪くなるような感覚が生まれてしまうのではないでしょうか。
スポーツや体を動かすことを考えた時、原理を考えてみると、体や道具を、無駄なく、いかに効率良く使い、最大限の力やスピードを発揮するか、ということに尽きると思います。たとえば、道具を使うのであれば、道具の力と自分の力を協調させて、最大限に発揮させる必要があります。
しかし、力を最大限発揮させようとすると、「自分の力を加える」ことをどうしてもしたくなってしまう、という傾向がないでしょうか?
コントロールするのではなく、観察し、感じることから始まる
さらに現代「只管打坐」講義では、このような指摘もあります。
息に向かってこちらから積極的に「手出し」、「介入」はしない。そこには息が「自分のもの」、「所有物」ではなく、息には息ならではの意思と智慧のようなものがあってそれを尊重しなければいけないという洞察がある。
例えばムチを振る動作を考えた時、ムチの動きを最大化させようとしたら、腕や手先の力は抜いて、腕を振り抜くような動きのほうが力が発揮されると想像できると思います。
ここで、腕で力を加えようと力んだ場合、むしろムチの動きは遅くなり、力が減少してしまいます。
良くいただく質問に、「力を抜くとムチが飛んでいってしまう」「力に負けてしまう」というご指摘をいただきます。
しかし、人間の身体の機能というのは素晴らしいもので、ムチを振る動作を力を抜いて、ほぼ握らずに行ったとしても、自然にムチが飛ばないように力を自動的に発揮してくれるのが、人間の身体に備わっている素晴らしい調整機能なのです。
では、ここで一つ質問です。
あなたは、道具や自分の体に対して、「コントロール」や「制御」して、動きを作り出そうとしていませんでしょうか?
自分が「主」であり、道具や自分の身体が「従」であって、自分が命令をして従わせる、という捉え方をしていませんでしょうか。
しかし、ここまでを踏まえると、自分が主体で、自分が道具や体をコントロールするのではなく、むしろ道具や体が主体であって、いかに自分はその邪魔をしないか、道具や体が力を発揮しやすいようにいられるか、ということになってきませんでしょうか。
そして、道具や体が力を発揮しやすいようにするために、自らの状態や道具の状態を観察し、自分の体がどのように動いているか、どの部分に力が入っているか、道具がどのような重さか、どのような速さで動いているか、を感じることがポイントになりますい。「制御」したり「コントロール」するのではなく、「観察」を行うことで、道具の「意思」や「智慧」が見え、それが見えてくると、自然とその力が最大限発揮されるように体の調整機能が作用し、一番良い力の使い方とフォームにつながっていきます。
まとめ
運動やスポーツに挑む中で、「力が抜けない」や「技術が向上しない」と感じている方は、力の使い方を見直すことで解決できます。体の使い方や力の使い方がどうなっているか、そして道具や自分の身体に対しての捉え方がどうであるかを振り返ってみましょう。捉え方が変わり、力の使い方が変わると自然とフォームも改善されます。そして、コントロールしようとするのではなく、自分の身体や道具を観察し、感じることが大切です。自分自身の内面を見つめ直し、力を引き出していくことで、あなたはきっと新たなステージへと進化します。
参考文献
Mind to move: Differences in running biomechanics between sensing and intuition shod runners