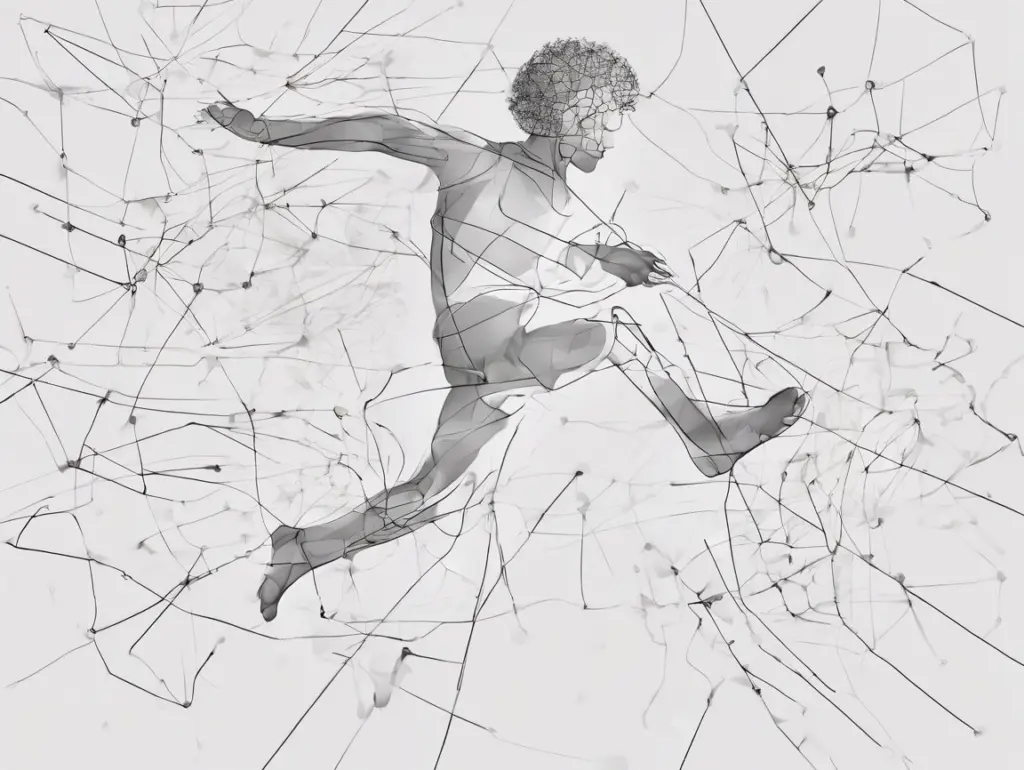
現場だけが上達の場ではない──思考を変えてスポーツパフォーマンスを高める方法
「練習しないとうまくならない」「たくさん練習をしないと上達しない」
スポーツの世界では、こうした考え方が長く信じられてきました。もちろん練習での実践は重要です。しかし、その意識だけに縛られていると、あなたの成長は知らず知らずのうちに止まってしまうかもしれません。
スポーツの動きは、あなたがこれまでの反復練習で覚え込んだものです。そこには、良いクセもあれば悪いクセもあり、何度も繰り返してきたために、それらは自動的に再生されます。これは一所懸命努力してきた証拠でもありますが、同時にそれらのクセを直すことがの難しさも表しています。
なぜ変わらないのか
試合はもちろん、練習の最中に新しい動きを身につけようとしても、多くの場合これまでのクセが顔を出します。スポーツの動きは、単一の動作ではなく、複数の動き・判断・認知が複雑に絡み合った総合パフォーマンスです。そうした複雑な状況に対応するために、脳はこれまで培ってきた自動的にできる動きを優先してしまいます。
ここで注目したいのが「脳は、実際に動いていなくても動いているように認識する」という事実です。
神経科学の研究では、動作を想像したとき、脳の運動野は実際の動作時とほぼ同じ活動パターンを示すことが分かっています。つまり、スポーツ パフォーマンスの観点から脳の活動を見れば、脳内で新しい動きをイメージすることは実際の練習と同じ神経回路を鍛えることになるのです。
脳内練習の強み
脳内で動きを再構成するとき、実際の練習のように複雑な状況や相手の動きに邪魔されることはありません。動作とは切り離し、純粋に「こう動きたい」という理想形を頭の中でイメージが描けるため、これまでのクセとは違った、新しいプログラムを作りやすくなり、これはスポーツ上達をするための思考法における有効なアプローチと考えることができます。
しかし、一方で、実際に体感したことのない動きはイメージしづらいという課題があります。そこで重要になるのが「捉え方」の修正です。
動きは単なる形ではなく、その動きをどういう力の使い方で発揮するかという「捉え方」から生まれます。捉え方を変えることができれば、動き方のイメージが変わり、結果として実際の動きも変わります。
上達の3ステップ:観察・問い・再構成
新しい動きを脳と体に定着させるための「捉え方」の変化は、以下のステップで実践してみましょう。自己成長していくためのメカニズムとして考えてみてください。
- 観察(客観視)
自分の動きを動画や他者のフィードバックで客観的に見る。理想と現実のズレを知ることが出発点です。 - 問い(前提を疑う)
「なぜこの動き方をしているのか?」を自分に問いかけてみましょう。今の動きを生むために、自分にどのような意図があるのか、動きを生み出している原因を探求します。 - 再構成(新しいイメージの構築)
成功事例をスローモーションで観察したり、自分の理想フォームをイメージしながら、今までの「捉え方」をどのように変化させることで新しい動き方を生み出すことができるのか、探りながら脳内で実践してみましょう。
新しいプログラムを試せてこそ練習
練習や試合は確かに重要ですが、新しいプログラムを自分の体に定着させたり、その精度を高めるためにある、と考えてみましょう。そのように考えると、練習の場だけで成長するわけではなく、移動中や休養中でも、脳内で新しい動きを探求し、描き続けることはできます。こうして探求した新しい「捉え方」「動き方」を、実際の練習の場で試し、定着させる、こうした実践こそが、持続的な成長を生みます。
プログラムを書き換える練習の考え方についてはこちら→フォームを直しても上達しない理由と改善法
まとめ
「練習しなければうまくならない」という思い込みを外し、脳と意識の使い方を変えることで、成長のスピードと質は大きく変わります。観察し、問いを立て、「捉え方」を再構成し、「捉え方」と「動き」を脳内で実践することで変化が生まれます。
