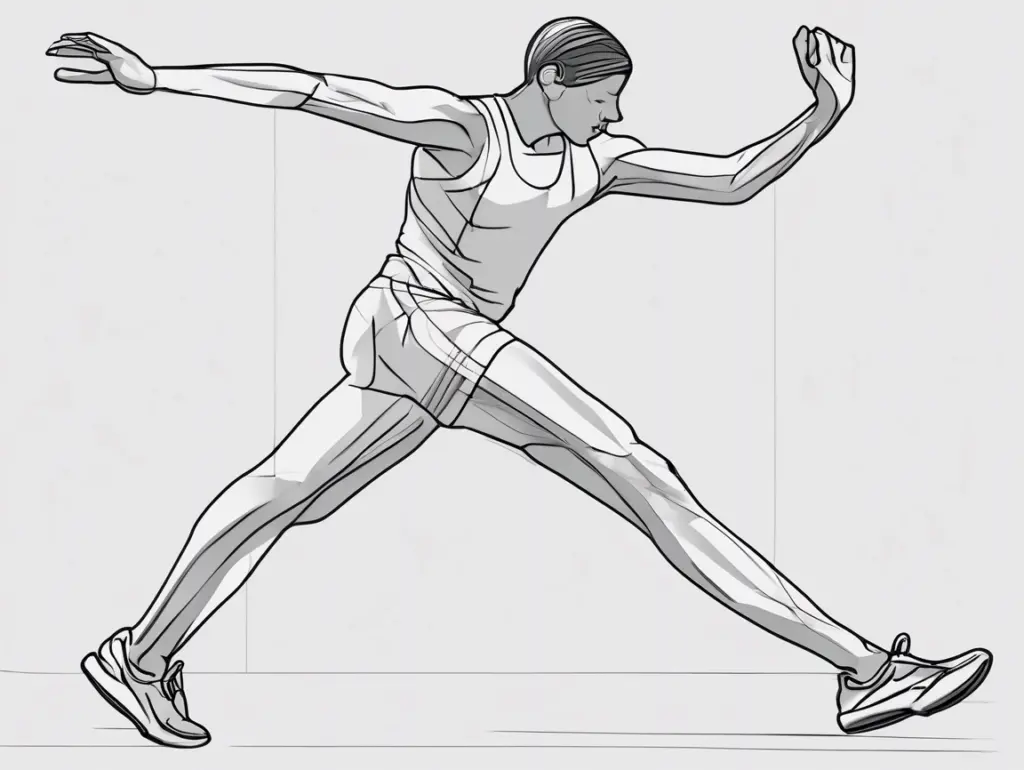
上達するということは、動き・認知・判断の“プログラム”を新しくすることです。多くの人はスポーツに取り組む時に、動きを改善した結果としてのフォームや型を意識して練習をしたり、あるいはその結果として発揮されたものを目標としがちですが、フォームや結果はあなたが生み出したものの確認の手段にすぎません。大事なのは、体のどこを、どのように動かすかという“中身”です。本記事では、動きを改善して成果結果を出すための方法を説明します。
まず理解したいこと:フォームだけ変えても中身が同じなら変わっていない
プロや上手な選手の動きを見て、フォームや型を真似しようという方も多いと思います。ですが、まずお伝えしたいのは、フォームや型を直したとしても、それを生み出している力の使い方や動かし方が前のままなら、動きの質は変わらない、ということです。
フォームや型、というのは、どのように体が動いたか、という動きの質が表れたものでしかありません。ということは外側の形だけを変えたとしても、内側の質に変化が生まれていなければ、変わってはいない、ということになります。例えば、振り抜くようなフォームにしたいと思って、腕の位置を振り抜く位置まで持っていくようにしたとしても、それは体が連動して腕の力が抜けていた結果として腕が振り抜かれて振り抜かれた位置にあるのであって、腕の力でその位置に作ったとしても動きの質には変化が生まれていない、ということになります。
一般的にアドバイスがされる時には「○○の形にしよう」と型やフォームの話が取り上げられがちですが、フォームや型は“結果”の一部です。それだけを追いかけると、前のやり方(旧プログラム)のまま、形だけが整いますが、質に変化が生まれていないので、結果にはなかなか結びつかないことになります。
なぜ“観察しながら”取り組むのか
当たり前のことですが、「目標としている動き」「目標としている結果」は、今の自分では出すことができないために目標としている設定しています。このように目標を設定して取り組むときでも、スタート地点は「今の自分」である、ということを改めて確認しましょう。
どれだけ目標を意識して取り組んだとしても、今の自分の動きを置き去りにして目標にたどりつくことはできません。ですので、今の動きがどうなっているか(どこに力が入る、どこが動いていない、どんな順番で動く)を理解して、はじめて目標の動きとの“差”を埋めることができます。そのために必要となるのが、観察です。
プログラムを変えようと取り組むときは、常に自分の動きを観察し、「いま、体の状態はどうか」「どこに力が入っているか」「体はどのように動いているか」「意識はどこに向いていたか」「どの条件ならできて、どうなるとできないか」といったことを問いかけながら取り組んでみてください。
「必ず新プログラムで取り組める」条件を作る
改善する動きがわかってきたら、練習で新しいプログラムを繰り返し練習しましょう。このときに、旧プログラムのまま動く練習をしてしまうと、旧プログラムがどんどん強化されます。ですので、新しい動かし方しか出ない条件で練習を取り組みましょう。ポイントは次の3つです。
- 狙いを一点にしぼる(例:手首の力みを減らす)。
- 他の要素をできるだけ消す(素振り/スロー/固定コースなど)。
- 難しさを調整する(できた→少し難しくする→またできた→少し難しくする→あまりできない→少し易しくする)。
具体的な進め方(4ステップ)
STEP1|狙いを明らかにする
例:「肩と体幹で始動して、腕はあとからついてくる」など、狙いを明確にします。
STEP2|他の要素を消す練習にする
素振り、超スロー、同じコース・同じ距離など、“やった→こう変わった”が分かる練習にします。
STEP3|難しさを調整する
できるようになったら、条件を一つ追加し、崩れたら少し易しくして、旧プログラムが出ない場をすぐに作り直します。
STEP4|「できた」はスタートライン
1回の成功ではなく、連続成功→無意識でも出るまで育てます。
競技別の「よくあるフォームアドバイス」と、どう簡単にして新プログラムで取り組むか
※ここでは一般的によく言われる、各競技でのアドバイス例を参考に、少し考えてみましょう。(各競技の専門ではないので、考え方の一例として捉えていただき、誤っているところがある場合ご容赦ください。)
テニス(ストローク)
- アドバイス例:「フォロースルーを肩に」
- 目的:体が回る力で腕が振り回されて、フォロースルーが肩まで振り抜かれる
- 起こり得ること:腕の力で肩まで腕を持っていこうとする
- 動きの質:腕の力が抜けて体が回る動きで、ボールの少し下から腕が振られることで自然に上方向に腕が振り回されてフォロースルーが肩に来るようになる
- 練習での取り組みの一例:フォロースルーが肩に来るのは、下から上に腕が振り抜かれた結果なので、フォロースルーの位置や形は確認の手段として、振り抜かれる感覚を重視して取り組む。
野球(打撃)
- アドバイス例:「軸足を残す」
- 目的:下半身が上半身と一緒にまわらないようにするため
- 起こり得ること:軸足に対する意識が強くなり、全身の連動と関係なく足を残そうとする
- 動きの質:下半身の回転で動きを生み、それを上半身に伝える際に、下半身の回転を止めることで上半身に伝える力を加速させることができ、下半身の回転が止まった結果として軸足が残る
- 練習での取り組みの一例:下半身から上半身への連動を感じながら動きを行い、上半身の動きが加速するような伝え方を取り組み、その結果として軸足が残っているか確認しながら取り組む。
サッカー(ファーストタッチ)
- アドバイス例:「足首を固定」
- 目的:ボールを受ける足首を正確に作りボールを正確に扱うため
- 起こり得ること:足首を力で固定して形を作ってしまい、ボールを受け止めるときの力の調整ができない
- 動きの質:力を抜いた状態で形を正確に作ることで、ボールの勢いに柔軟に対応することができる
- 練習での取り組みの一例:力を抜いた状態でも自分の足首がどのような状態かを観察できるようにして、ボールを受ける形を力が抜いたままでも作れるようにする
バスケットボール(シュート)
- アドバイス例:「手首のスナップ」
- 目的:バック回転をかけて弾道を安定させるため
- 起こり得ること:手首の力でスナップの動きを作ろうとしすぎて、手首の動きが正確にボールに伝えられていない
- 動きの質:腕から伝わった力をボールに伝えようとするときに、手首の力が抜けていることで自然に手首のスナップの動きが生まれてボールに力が伝わる
- 練習での取り組みの一例:腕から伝えた力をボールにていねいに伝えれているかを観察しながら取り組み、その結果として手首が自然に動いているか確認しながら取り組む
卓球(バックブロック)
- アドバイス例:「前でさばく」
- 目的:打点が遅れないようにして自分が振りやすい場所で打つため
- 起こり得ること:自分の振りやすい状態ではなくても前でさばいてしまう
- 動きの質:コンパクトな準備と相手の球への素早く無駄のない反応を行うことで、前でさばくことができる
- 練習での取り組みの一例:前でさばけていないときに、準備や振りに行く動き、あるいは相手が打つときの意識の状態を観察して、対応が遅れた原因を振り返りながら取り組む
バレーボール(サーブ)
- アドバイス例:「体重移動を大きく」
- 目的:体重移動の力をボールに伝えるため
- 起こり得ること:体重の移動はされているが、その力がボールに伝えられていない
- 動きの質:体重が移動する力が、体の連動した動きとつながって、ボールに伝えられる
- 練習での取り組みの一例:ボールに伝える力がどのように生まれているかを観察しながら取り組み、体重移動の力をボールに伝える連動を意識しながら取り組む
まとめ
- フォームや結果は確認の手段。主役は**体の動かし方(プログラム)**です。
- 観察によって今の動きを正しくつかみ、目標との差を埋めます。
- 必ず新プログラムで動ける条件を作り、難しさを調整しながら連続成功を増やします。
- できたら終わりではなく、無意識でも出るまで育てる。
遠回りに見えて、これがいちばんの近道です。必要なら、各競技の「フォームアドバイス例」にあなたの視点を追記して、現場に合わせた練習に落とし込みましょう。
