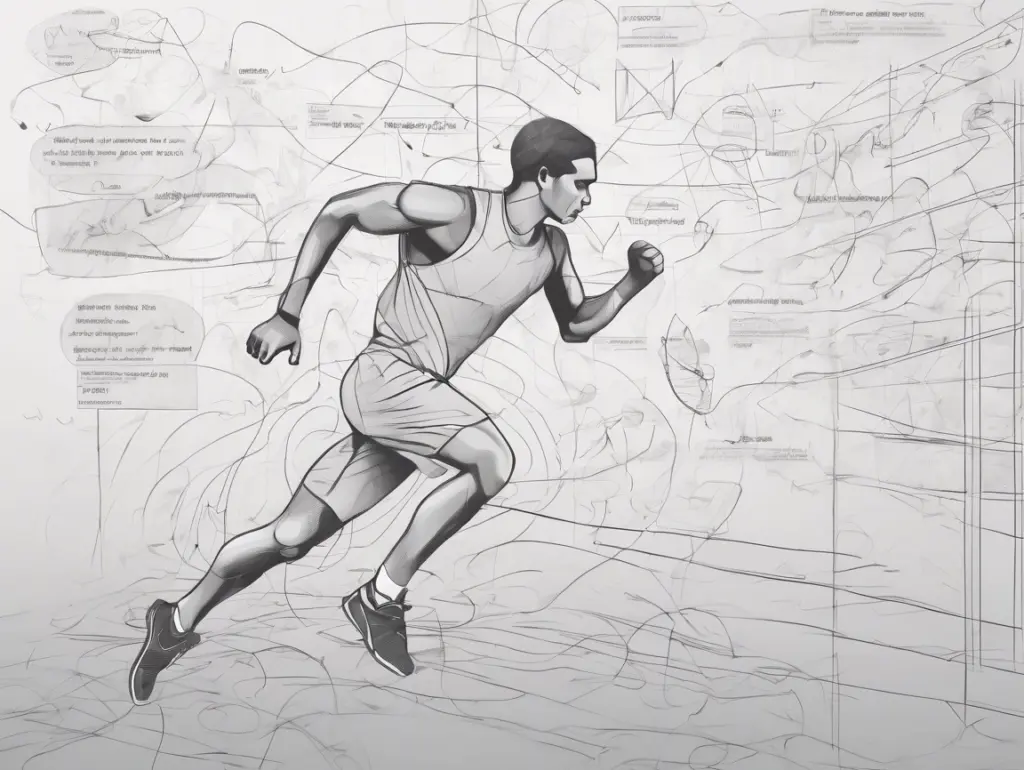
「頑張っているのに成果が出ない」「努力しているのに結果につながっていない」─競技に取り組んでいると、こうした悩みを感じる方も多いのではないでしょうか。そのとき、つい“気持ちの問題”や“やる気の差”に原因を求めてしまいがちですが、それは本質的な解決にはつながりません。
本記事では、技術や成果の“原因”を適切に捉える視点の重要性と、「原因と結果」のつながりに注目した練習の考え方について紹介します。
うまくいかないときによくある“誤った捉え方”
うまくいかなかったとき、誰しもが自分なりに原因を考え、改善に取り組んでいると思います。しかし、原因に取り組んだけれども結果が変わらず、諦めてしまった、ということはないでしょうか。そうしたとき、このような”誤った捉え方”をしているかもしれません。
1. 「努力が足りない」
結果が出ないのは、単に努力が足りなかったから──という捉え方は根強いですが、努力の「方向」や「質」が間違っていたらどれだけ努力をしても間違った方向へ進んだり、時には怪我をしてしまうかもしれません。がむしゃらな努力ではなく、どこにどう働きかけるかを見極める視点が必要です。
2. 「やる気がない」
「やる気がない」ことが原因だと考え、自分の怠け癖を責めたり、とにかく一所懸命取り組むことが大切だと捉えてしまうことがあります。しかし、実はやる気の有無ではなく、「何に取り組んでいいかわからない」「できない理由が見えていない」ことが背景にあり、どう努力したらいいのかがわからないからやる気が出ないのかもしれません。
3. 「集中力が続かない」
集中力の低下も一因にはなり得ますが、「何に集中するべきか」「それに集中したときにきちんと改善が見えているか」を振り返るとどうでしょうか。集中するべきことがあいまいであったり、集中して取り組んでもいっこうに改善が見られなければ、集中力が続かないのは当たり前です。
4. 「調子が悪かった」
一時的な不調に原因を求めるのは簡単です。特に、うまくいっている理由、うまくいっていない理由がわからないと、調子の波によってプレーが決まってしまう、という考え方になってしまいます。しかし、もしもうまくいく時にはうまくいく原因が、うまくいかないときにはうまくいかない原因があるとしたら、それをつぶすことで調子の波は限りなく小さくなるかもしれません。
5. 「いつも通りじゃなかった」
試合の空気感やプレッシャーによって「いつも通り」が出せないのはよくあることです。いつも通りが出せないときも、どのようにしていつも通りになっていないのかが理解できていれば、いつも通りにはならないかもしれませんが、少なくとも落ち着いたプレーができます。
6. 「相手が強かった」
相手の強さは確かに結果に影響しますが、もう少し掘り下げて考えてみましょう。どこが通用していてどこが通用していなかったのでしょうか。具体的な課題にすることで、もしかしたら思っている上に戦える部分が見つかるかもしれません。もしかしたら自分のイメージの中で作り上げた「強さ」も、一つ一つていねいに分析・観察することで、もう少し変わった見え方になるかもしれません。
結果には物理的な原因がある
課題やミスが生じる背景には、メンタルや気持ちの問題という側面もありますが、必ず直接の結果に結びつく“物理的な原因”があります。たとえば、スイングがズレるという結果があるとき、その原因は単に「集中していなかった」のではなく、集中していないことによって、タイミングの取り方やステップ、相手やボールの動きに対する気付き、といった、物理的な動きや認知のどこかにズレがあることにより、いつもと異なる動きにつながり、ミスや課題につながっています。
この“原因”を、感情や気分のせいにしてしまうと、本当の原因である体の動きや気づきについての改善ポイントを見逃してしまいます。
また、体の構造や筋力、柔軟性、過去の動きのクセといった“身体の特徴”が影響していることもあります。たとえば、「スピードが出ない」という課題があるとき、それは筋力の問題かもしれませんし、フォームの効率性、あるいはスタートのタイミングや足の接地感覚といった複合的な要素かもしれません。つまり、「一つの原因で説明できることの方が少ない」という前提に立つことで、初めて本質に近づくことができるのです。
原因を探し当てる
しかし、なぜ原因に取り組んでいるのに結果が変わらないことが起こるのでしょう。
それは、ある結果に対する原因が1つとは限らず、複数の要因が絡み合っていたり、より原因の奥にさらに根本的な原因が隠れている、という仕組みになっていることに気づかず、自分が思い当たる原因が本当の原因だと思い込んで取り組むので、原因に取り組んでいるのに結果が変わらない、ということが起きてしまいます。
ですので、選手が原因として挙げた要素に取り組んでも、うまくいかないことが起きてしまう背景には、(1)原因が複数あり一部しか捉えられていない場合、(2)もっと根本的な原因が隠れていて表層の修正では不十分な場合、(3)そもそも原因と結果の関係を十分に理解できていない場合、などが考えられます。つまり、原因を探すプロセスそのものを丁寧に行い、深掘りと仮説検証を繰り返すことが求められるのです。
たとえば、スイングのタイミングがズレたという結果に対し、「もっと集中しよう」とメンタル面に原因を求めたとします。でも、実は足の運びが遅れていたり、相手のボールの変化に対応しきれていなかったりといった要因があるのかもしれません。それなのにただ「集中しよう」と取り組んでも、本当の原因が改善されないことになってしまいます。
このように、目に見える結果の背後には、いくつもの原因が複雑に関係しています。「なぜうまくいかなかったのか?」を一緒に深掘りしていく姿勢があることで、根本からの改善につながります。
因果関係を明確にする問いかけ
たとえば、このような問いかけを自分にしてみましょう。
- 「そのミス、どの場面で起きやすい?」
- 「練習ではできてたとしたら、何が違った?」
- 「できたときと何が違う感覚だった?」
このような問いを通して、“できなかった結果”を振り返り、そこに至る「原因」を言語化できるように促します。「たまたま」や「気持ちの問題」で片付けるのではなく、自分の行動や判断、準備、タイミングなど、具体的な要因を洗い出すことが重要です。
そして、思いついた原因で満足するのではなく、それが本当の原因ではないかもしれない、もしくは原因の原因があるかもしれない、という姿勢で、練習で確かめながら取り組むことで、本当に原因にたどりつけます。
自分だけの地図を描くために
一人ひとりの体の動き方や考え方、これまで積み上げてきた経験は異なります。だから、他人のアドバイスは“その人にとっての成功の地図”であって、自分にとっての正解とは限りません。
つまり、自分自身の「原因と結果」のつながりを探求し、理解してはじめて、自分の成長ルートが見えてくるのです。
だからこそ、たとえ同じ課題・同じミスでも、人によって取り組むべきやり方や順序が異なることがあるのです。他人の成功法則やコツを鵜呑みにするのではなく、課題の原因は何なのか、なぜそのような課題が発生したのか、ていねいに原因を探ることで、自分の中の「上達の地図」が明らかになっていきます。
まとめ:課題には、必ず“理由”がある
課題やミスには必ず“原因”があり、その結果として“できなかった”という現象が現れます。
「なぜそれが起きたのか?」と問う姿勢が、技術を深め、成長を支える礎になります。原因を明確にすることができれば、あとは改善の工夫を積み重ねるだけです。
目に見える“結果”に振り回されるのではなく、その背景にある“原因”を探るプロセスこそが、真の成長につながります。
