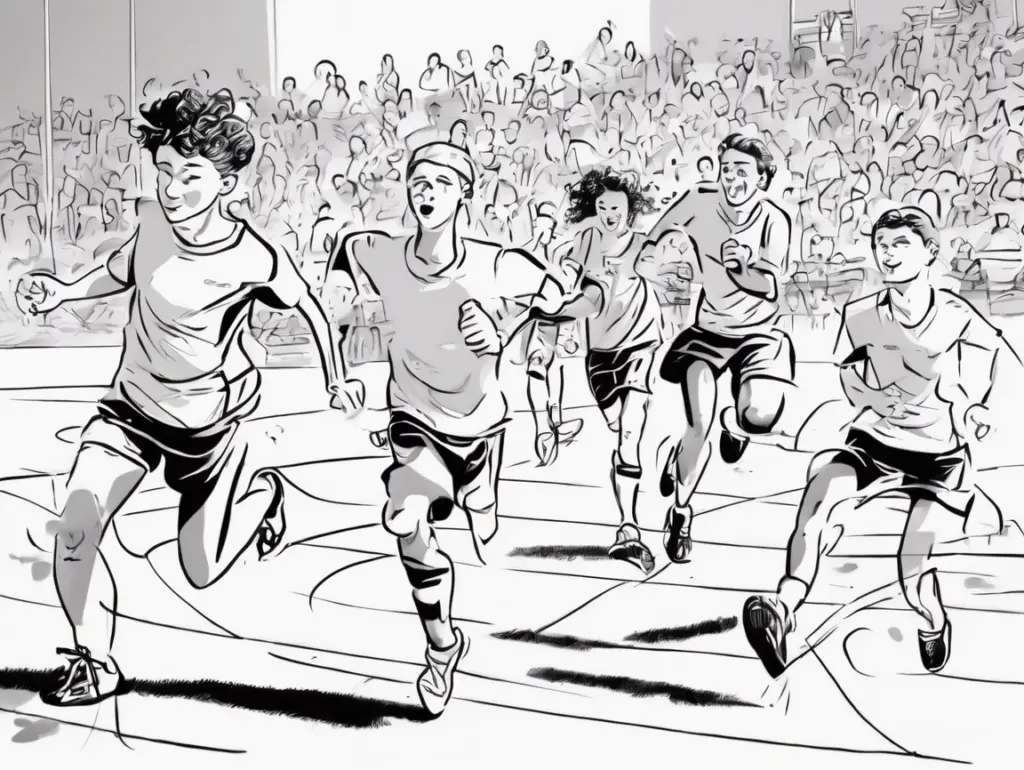
「最近の子は諦めが早い」「目標に執着しない」と言われることがあります。昔のように歯を食いしばってやり抜く姿勢は少なくなったかもしれません。しかし、それは必ずしも“気持ちが弱い”からではありません。今の時代に合った粘り強さをどう育むかを考えることが大切です。
昔の「気持ちの強さ」とは?
親や先生の世代においては、子どもや生徒の「気持ちの弱さ」が目についてしまうかもしれません。「もっと踏ん張ってほしい」「諦めずに取り組んでほしい」という願いがあってのことだと思います。そうしたときに立ち返りたいのが、「そもそも『気持ちが強い』とは何を意味するのか?」という視点です。ここでは、まず昔のスポーツ現場で評価されてきた“気持ちの強さ”とは何だったのかを整理し、そのメリットとデメリットを見つめ直してみたいと思います。
まず気持ちの強さを整理すると、「我慢する力」「従順さ・自己犠牲」「結果至上主義」と言えるのではないでしょうか。
我慢する力
たとえどんなに辛くても、逃げずに最後までやり抜く。理不尽に耐える力、我慢や忍耐の強さが、当時のスポーツ現場では大きな美徳とされていました。叱責を受けても泣かず、歯を食いしばって乗り越えることが「気持ちが強い」と見なされやすかったのです。
従順さ・自己犠牲
「上からの指示に従う力」もまた、かつての強さの象徴でした。指導者の言うことには疑問を挟まず、ただ黙々と与えられた練習をやり抜く。自己犠牲的に時間や体力を差し出すことが、努力の証とされる時代背景がありました。
結果至上主義の精神
プロセスよりも、結果を重視する文化も根付いていました。ケガをしていても試合に出る、体を壊してでも勝ちを取りにいく、その姿勢に「気持ちの強さ」を重ねて見ていた人は少なくありません。
当時は「厳しい環境を耐え抜くこと=強い気持ち」という価値観が一般的でした。
では、こうした「気持ちの強さ」におけるメリットとデメリットを整理してみましょう。これは、今の子どもたちに求める“強さ”とはどう違うのかを考えるための出発点にもなります。
メリット
- 苦しい状況でも簡単に投げ出さない粘り強さを養える。
- 困難を乗り越えたという成功体験が自信につながる。
- チームにおける責任感や継続力が評価され、勝利や成果に直結する場面も多かった。
デメリット
- 無理を重ねてケガや燃え尽きにつながりやすい。
- 指導者や環境への従順さが優先され、自分で考える余地が少なくなる。
- 「耐えること」自体が目的化し、技術的な改善や創意工夫が後回しになるリスクがある。
こうした背景を踏まえると、「気持ちの強さ」という言葉に込められた意味もまた、時代とともに変わっていく必要があるのではないでしょうか。
今の子どもたちを取り巻く環境
現代の子どもたちは、かつてとは大きく異なる環境の中で育っています。日々膨大な情報に触れ、SNSや動画では「効率よく成功する姿」や「才能ある人がうまくいく過程」が数多く目に入ります。
また、学校や家庭では「自分で考えて行動すること」「将来の選択肢を広げること」が強く求められ、一見すると自由度が高いようでいて、実際には「失敗しないように選ぶ」「間違えないように動く」ことにエネルギーを使っている子も少なくありません。
その結果、チャレンジの前に“失敗するぐらいならやらない方がいい”という感覚や、“頑張っても無駄かもしれない”というあきらめが先に立ちやすい傾向が生まれています。
さらに、現代の子どもたちはとても繊細で、感情への感度が高い傾向にあります。周囲の視線や評価に敏感で、「ちょっと注意されただけで立ち直れない」「小さな失敗で大きく落ち込む」といった姿もよく見られます。これは一見“気持ちが弱い”ように見えるかもしれませんが、むしろ感受性が豊かだからこそ感じ取っていることでもあります。
今の子どもたちが持つ強みと可能性
一方で、今の子どもたちは非常に多様な価値観に触れながら育っており、他者への共感力や、状況に応じた柔軟な対応力を備えている世代でもあります。感情を言葉にする力、仲間との協調性、自分なりの意味づけを模索する力など、目には見えにくいけれど確かに成長の土台となる力を持っています。
また、昔に比べて「正解のない問い」や「変化の激しい社会」にさらされている分、自分で考え抜く力、必要な時に助けを求める力、複数の視点から物事をとらえる力など、“しなやかさ”を活かした強さが育ちやすい環境とも言えます。
そのような力をどう活かし、どう支えるか。それこそが今の時代における「気持ちの強さ」を育む鍵となっていきます。
粘り強さを育むために大切なこと
では、どのようなときに、どのようにしたら、“気持ちの強さ”は育まれるのでしょうか。
まず大切なのは、子ども自身が「意味がある」「やってみたい」「なんとかなるかもしれない」と前向きに感じられる状況を整えることです。これは単なる根性や精神論ではなく、「信頼関係がある」「安心して失敗できる」「今の自分にちょうどよい挑戦である」といった複数の環境的要素がそろうことで生まれる、内発的な粘り強さです。
このような状態を引き出すには、周囲の大人の関わり方が極めて重要になります。「失敗したくない」という自然な気持ちにまず寄り添い、その上で「失敗しても受け入れてもらえる」と感じられる空気を育てていく必要があります。思いや選択を頭ごなしに否定せず、選べる自由を持たせ、「自分で決めて、自分でやり抜く」体験を積み重ねることが、子どもにとっての自信となり、やがて粘り強さの基盤になります。
昔のやり方に対する理解と問い直し
とはいえ、今の保護者や指導者の中には、「自分たちはそんなふうに育てられてこなかった」「厳しい中でもなんとかなった」と感じる方もいるかもしれません。実際、過去のやり方で育った世代の中にも、粘り強く成果を出してきた人は多く存在します。
しかし、現代の育成環境を見てみると、主体的に関わり、自己決定の中で努力する選手たちが、より長く・深く成長する傾向にあることも見逃せません。たとえば、大谷翔平選手のように、自ら目的や行動を明確にし、楽しみながらも高い目標に挑む姿勢は、まさに信頼と内発的動機づけによって育まれた強さの好例です。
厳しく育てられた経験から、こうした接し方を単なる“甘やかし”や“放任”と捉えることも可能ですが、主体的に取り組むというのは、自らの意思で向き合う責任を持つということでもあります。そして、内発的に動機づけられた努力は、長期的な成長や持続力、創造的な問題解決力に繋がることが、多くの研究や実践からも示されています。
さらに、「厳しさに耐えて強くなった」という経験があるからこそ、今の子どもたちへのアプローチを変えることに戸惑いが生まれるのは自然なことです。しかし、育成の目的が「よりよく育つ」ことにあるのなら、子どもの置かれている環境や時代背景に合わせて、方法や接し方を見直すことは、決して過去を否定することではなく、新たな可能性に向けた更新です。
「今のやり方は甘いのではないか」という心配は、「今の子にはどうすれば粘り強さが育つのか」という問いに転換できます。自分の経験と照らし合わせながらも、「こうあるべき」ではなく、「今だからできる関わり方」を模索する視点が、結果的に子どもの成長を後押ししていくのではないでしょうか。
粘り強さを育む5つのポイント
1. 小さな成功体験を積ませる
難しすぎる課題はすぐに諦めにつながります。達成可能なスモールステップを設計し、「できた!」を積み重ねることで、続ける意味や成長実感を得られます。特に、うまくいかない時期にこそ、小さな達成を言語化して振り返ることが、再挑戦への意欲を引き出します。目に見える形で達成を記録し、本人が「できた」と自覚できるようにしましょう。
💡「スモールステップの設計での練習」については、こちらの記事も参考にしてください:
👉上達の近道は遠回りに見える——小さな結果を積む理由
2. 失敗を安全に経験できる環境
失敗を責められたり恥と感じたりする環境では、人は挑戦を避けがちです。失敗が自然なプロセスとして受け止められる環境は、「失敗しても大丈夫」「また挑戦できる」という安心感を生みます。そのためには、再挑戦の機会を仕組みに組み込み、失敗の中身を一緒に言語化していくことが大切です。罰や否定ではなく、調整と再試行を支える空気を育てましょう。
3. 過程を認めるフィードバック
「よく頑張ったね」だけでは伝わりません。粘り強さを支えるのは、「どこをどう工夫したのか」「どんな点がよかったのか」という具体的なフィードバックです。結果だけでなく、過程に価値があるという視点で見てくれる人がいると、子どもたちは挑戦し続ける勇気を持てます。観察→評価→提案の流れで、次の取り組みへの足がかりをつくっていく関わりが重要です。
4. 選択肢と自己決定の余地を残す
「自分で選んだ」という実感は、継続や努力の大きな原動力になります。反対に、「やらされている」「選べない」と感じると、粘り強さは生まれにくくなります。本人が選択肢を持ち、その理由を考えることで、意思を持ってやり切る経験が生まれます。また、選んだ後にサポートやフィードバックを得ることで、自分の選択に責任と意味を見出せるようになります。
5. 将来とつなげる問いかけ
「なぜ今これに取り組むのか?」「この経験がどんな場面で活きるのか?」を考えることで、粘り強さは一時的な頑張りではなく、将来を見据えた持続的な力へと変わっていきます。意味づけを通じて努力に納得感が生まれ、途中での迷いや挫折への耐性も高まります。
ただ目の前の練習や課題をこなすのではなく、「これがどう活きるのか?」「今の自分にどんな変化をもたらしているか?」といった問いを持ちながら取り組むことが、長期的なモチベーションにつながります。こうした問いを通じて、現在と未来の自分を結びつける視点が育まれます。
おわりに
「気持ちの強さ」は、時代とともにその意味を変えてきました。かつては耐えることや我慢することが強さとされていましたが、今の時代には“しなやかに考え、粘り強く行動する力”が求められています。その力を育むには、大人たちが信頼と安心を土台にした関わりを意識し、子どもたちが自らの意志で挑戦し続けられる環境を整えていくことが重要です。
過去の経験を尊重しながらも、今の時代にふさわしい育成のあり方を問い直し、子どもたちの中に眠る可能性を信じて関わること。それこそが、これからの「気持ちの強さ」を育む第一歩となるのではないでしょうか。
