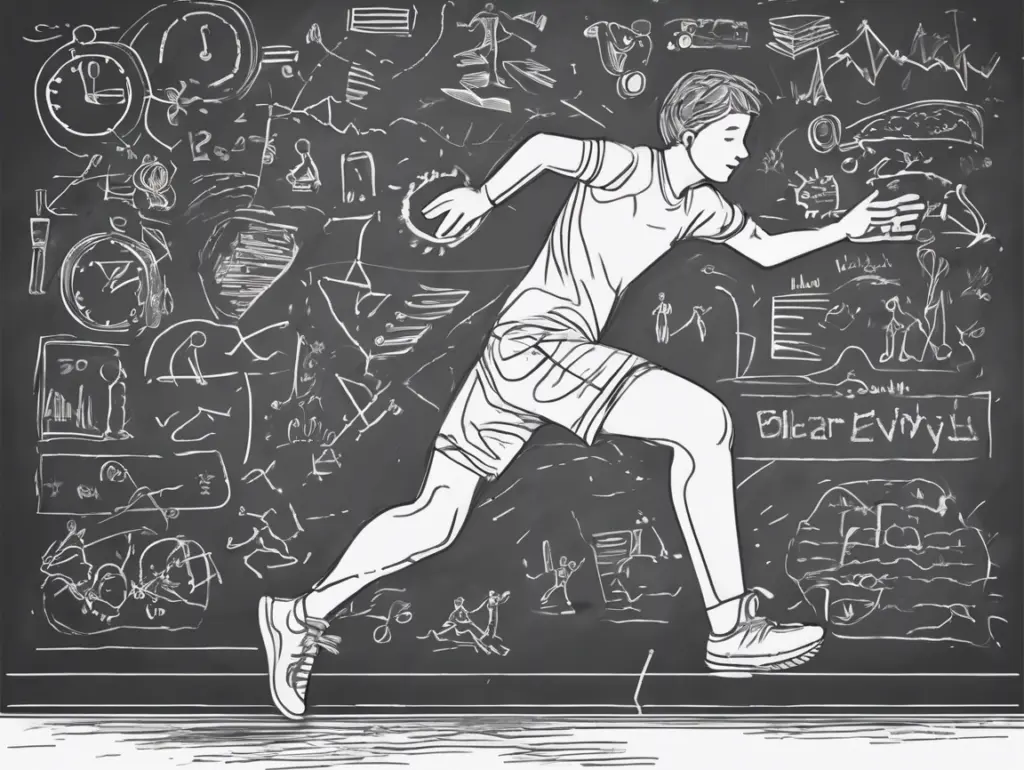
「スポーツをやる意味」とは?
「スポーツをやらせる意味は?」「本当にスポーツは将来 役に立つのですか?」——保護者や指導者の方なら、一度は考える疑問だと思います。何事に取り組んだとしても、真剣に一所懸命取り組めば“学び方”“物事への取り組み方”は身につきますが、ここではスポーツの意味(スポーツ 意味)を「学び方を身につける場」として捉え直してみましょう。
スポーツにおいては、すぐに結果(フィードバック)が得られる・トライ&エラーを大量に回せる・体で具体化できる・ゲーム性があって楽しみながら続けられる・感情が動く・主体的に取り組みやすい、といった点で、特に学びが得られやすく、自立した学習姿勢(自分で課題を見つけ、試し、直し、次に進む力)を育て、学業や将来役に立つ力へとつながっていくと考えられます。
自立した学ぶ姿勢とは?
スポーツに限らず勉強・芸術・仕事など、あらゆることに取り組むときには、見る → 考える → やってみる → ふり返るといった“学びの作法”が必要となります。これらの姿勢は、一つの分野に限られたものはありません。スポーツでこの作法を体得することが、将来役に立つものにつながると考えられます。
- 見る(事実で観察する)
- 内容:感想や印象ではなく、事実を観察して正しく現状を把握します。事実が定まらなければ、原因も対策もぼやけてしまい、原因と結果の線がつながらなくなってしまいます。
- 身につくとどうなるか:問題の焦点が明確になり、無駄な努力が減り、改善速度が上がります。勉強なら「何が自分の苦手か」といったことがわかるようになります。
- 考える(原因と打ち手を一つに絞る)
- 内容:大きな課題を因数分解し、いま試せる仮説を1つに決めます。ある結果には必ずそれを生み出した原因が存在します。原因を特定し、改善することで結果が変化する、という視点を手に入れることで、結果を変えるスタート地点に立つことができます。
- 身につくとどうなるか:目先の結果ではなく、原因を探求し、本質的な解決をするための考え方や行動を取ることができます。また、原因を考える姿勢は、目先の結果に心が左右されない強さも手に入れられます。
- やってみる(短く素早く試行する)
- 内容:考えた原因を、小さく・早く試して、原因だと思っていたものが正しいのかどうか、確かめます。自分では原因だと思っていたものが、実はそうではないかもしれません。試してみることでこそ、その正しさがわかります。
- 身につくとどうなるか:自分の思い込みで行動したりするのではなく、原因を確かめるような行動ができるようになります。
- ふり返る(次の一手に変換する)
- 内容:結果から得られた学びを次の具体的行動に落とします。この振り返りを通してこそ、正しい結果を導くための正しい原因を探し当てることができます。
- 身につくとどうなるか:試行が学習資産に変わり、安定して成果を再現できます。失敗の原因がはっきりとしてくるので、失敗したときも慌てずに取り組むことができ、テストでも本番でも“同じようにできる”状態になります。
”学び方”から考える”スポーツ”
それでは、勉強やその他のことと比較したときに、スポーツに取り組むことには、どういった良さがあるのでしょうか。
- すぐに結果(フィードバック)が得られる
練習においては、すぐにその場で試したことの「良かった/悪かった」が分かるため、原因と考えていたことに対するフィードバックを得ることができます。すぐに結果が出るので、原因と考えていたことが間違っていたときに、修正をすぐにかける姿勢が身についていきます。 - トライ&エラーを大量に回せる
1回の練習において、たくさんの試行ができるので、小さな失敗を安全に積み重ねることができます。失敗への耐性が身につき、新しい方法を恐れず試す姿勢が身につきます。この反復経験は、将来の様々な場面で役に立つ力になります。 - 体で具体化できる
「頑張れ」といった精神的なことや抽象的なことではなく、「面の角度」「足の向き」「打つ位置」「力の感覚」など直す場所が明確でないと改善ができないので、具体的に取り組む力が身につきます。抽象的な課題を具体的に分析する力が磨かれ、何かを解決するときに同じような取り組み方で臨むことができます。 - ゲーム性があり、楽しみながら続けられる
言うまでもなく、スポーツにはルールや得点といったゲーム性を伴うものなので、楽しみながら主体的に取り組むことができます。そのため続けやすく、習慣化が進みます。 - 感情が動く
生きていくうえでは、様々な場面で自分の感情と向き合うことになりますが、スポーツにおいてはそうした自分の感情と向き合う場面が数多く訪れます。そうした場面を通して、自分の感情との向き合い方や自分がどういった感情を抱えているのか、といったことへの気づきをもたらします。 - 試合という“本番”を通しての学び
定期的に訪れる試合を通して、それまで自分が取り組んできたことの成果を確認できます。それらを通して、自分の取り組み方を振り返るきっかけになり、気付きや学びにつながります。
将来役に立つ、スポーツを通して身につく「7つの力」
1. 自分を見る力(自己観察)
自分を見る力とは、「今日はダメだな」といったものではなく自分を客観的に観察することです。自分を客観的に観察して事実で見られるようになると、余計な遠回りが減り、直す一歩がすぐ決まるようになります。これは「改善する力」「取り組む力」を育てる最初の土台になります。
2. 課題を小さく分ける力(問題分解・設計)
大きな課題を小さく分けて、できることから取り組むことは何かを考えて実践することです。あれもこれも一度に直そうとしたり、大きな課題にそのまま取り組もうとしても、何が効いたのか分からなかったり、変化が生まれません。小さく分けられると、今やることがハッキリしてきます。
3. 試してすぐ直す力(小さなトライ&エラー)
「こうすれば良くなるはず」と考えたことを短い時間で試し、結果を見てすぐ直す力です。考えているだけでは分からないことが多く、やってみて初めて見えることがあります。小さく回せるようになると、行き詰まりが短くなり、改善のスピードが速くなります。
4. ことばにする力(言語化)
フォームやタイミング、力の入れ具合など、あいまいなものを言葉にすることで、抽象的なものを具体的なものにする力が身につきます。言葉にすることで、コツや感覚を再現することができるようになります。また、自分の感情もことばにできるようになることで、自分を表現する力が身につくとともに、自分の中にある感情を客観視して冷静に対応していくことができるようになります。
5. 気持ちを整える力(感情の自己調整)
緊張や焦り、不安といった感情に気づき、冷静に対応していくことができます。本番で気持ちが揺れるのは当たり前で、否定するよりその生まれてくる感情の扱い方を持っていることが大切です。感情の扱い方を訓練していくことで、感情が生まれてくる様々な場面でも同じように向き合うことができます。
6. 本番から逆算する力(準備と当日の動き)
試合などの本番から逆算して準備を組み、計画を立て、取り組み、試合が終わったら振り返る力です。本番でたくさんことをやろうとしてもはできることが限られるので、それまでにどれだけ準備を行い、体が動くことができるようにできるか、準備の質が結果を大きく左右します。逆算できるようになると、優先順位がブレず、当日も落ち着いてやるべきことに集中できます。終わった後の学びも、次へしっかりつながります。
7. ふり返って続ける力(継続の仕組みづくり)
結果を「良かった・悪かった」で終わらせず、何が起きたか→なぜか→次に何をするかへつなげ、継続して改善する力です。自分が取り組んできたことの結果として表れたものを見つめることで、それまでの自分を見つめ直すことができます。ふり返りができると、負けや失敗が学びの入口に変わり、少しずつの前進が積み上がるようになります。
負けや失敗をどう捉えるか
このように考えると、スポーツの本質的な意味は勝ち負けそのものではなく、物事にどのように向き合い、取り組み方をつくっていくかにあると考えられるのではないでしょうか。技術や根性だけを積み増すのではなく、「どう考えるか」「どう体を使うか」「どう心とつき合うか」を結び直して、自分なりの上達の道をつくる——その視点に立つと、結果は通過点であり、取り組みの質こそが価値になります。
失敗は、避けるべき出来事ではなく、原因だと思っていたことがどこでズレていたかを教えてくれるはっきりした合図だと言えます。うまくいかなかった一本、競り負けたセット、緊張で固まった場面——それらは能力の不足証明ではなく、今のやり方の「改善ポイント」を示すサインです。だからこそ、試合や練習のあとには、まず事実(何が起きたのか)を振り返り、つぎに原因(どの動き・判断・準備が影響したのか)を考え、次の一手(明日やる具体的な行動を一つ)に変えて実行します。こうして経験を通して、結果がをもって“良かった””悪かった”で終わらせず、“次の行動”へつなげることで、負けや失敗は学びの入口へと姿を変えます。
この捉え方が身につくと、結果に一喜一憂して消耗するのではなく、立て直す力(心の粘り)と直し方を設計する力(学びの設計力)が育ちます。たとえ逆風でも、事実→原因→次の一手の順に淡々と前へ進めるので、スポーツの場面はもちろん、生きるうえでの様々な場面でも、落ち着いてやるべきことを選び直せるようになります。負けや失敗を価値のある材料として扱えること——それこそが、スポーツをする意味であり、将来にわたって役に立ついちばん大きな力だと考えられるのではないでしょうか。
よくある質問
Q. 勉強時間が減るのが不安です。
A. 重要なのは“量”だけでなく質です。スポーツで【見る→考える→やってみる→ふり返る】を覚えますと、短時間の取り組みでも成果が出せていくようになります。
Q. 勝てないなら意味がないのでは?
A. たしかにそのように感じることもあるかもしれません。しかしスポーツに取り組む意味を“学び方を身につけること”と捉えると、負けから課題を見つけ直す力が育ち、結果的に将来役に立つ学びに変わると考えられます。勝てなかったことが大きな力につながる、と捉えることもできるのではないでしょうか。
まとめ
何事でも一所懸命に取り組めば「学び方」「取り組み方」は身につきますが、スポーツは即時の結果・大量の試行・身体での具体化・楽しさ・感情・主体性・試合という本番といった体験を通した学びがあると考えられます。
自分で課題を見つけ、言葉にし、試して直す。 こうした姿勢は一生の財産です。勉強かスポーツかの二択ではなく、スポーツで学び方を身につけ、それを勉強と将来に生かす——ここに「スポーツの意味」と「スポーツは将来役に立つのか」に対する答えがあるのではないでしょうか。
