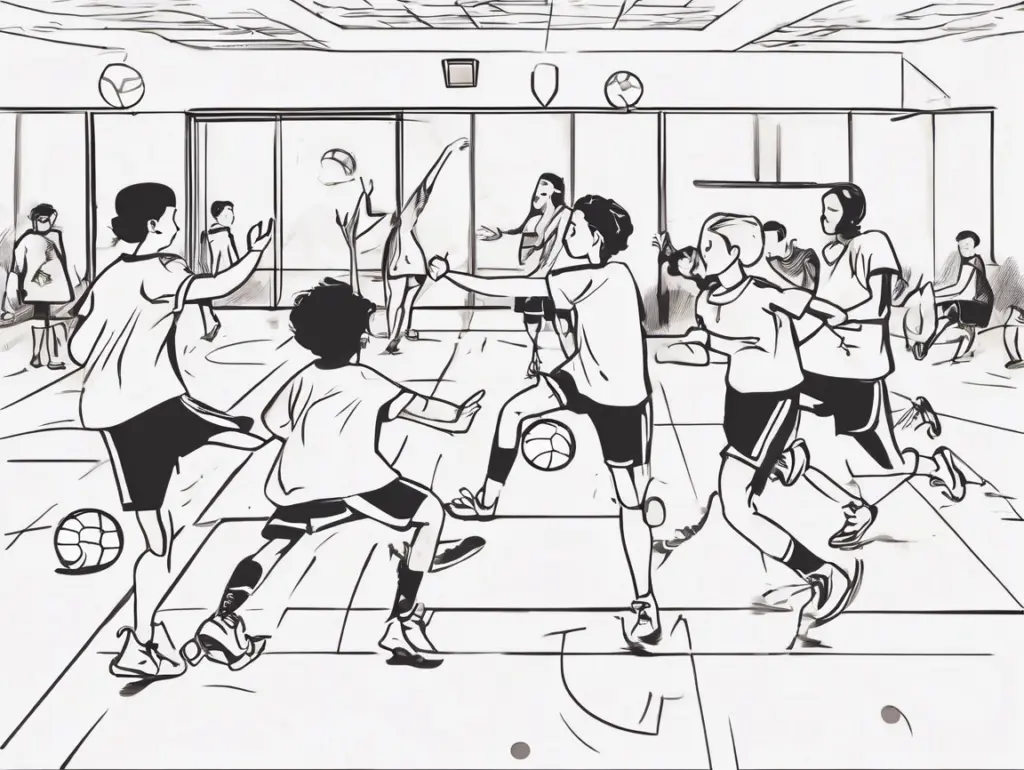
部活動指導の悩みと対策
「指導方法がわからない」「部活の指導法に悩んでいる」──そんな先生や指導者の方の声は少なくありません。部活動で生徒を指導する立場にある方が直面する悩みは多岐にわたり、特に「どう教えればよいかわからない」「何が正しいのか自信が持てない」と感じられている方が多くいらっしゃいます。また、競技経験の有無にかかわらず、育成の方法や関係づくり、チーム運営など、様々な場面で戸惑いや不安を感じることもあるのではないでしょうか。
部活動においては、関わる生徒や選手、そして先生・指導者、あるいは保護者の方のそれぞれの方が、それぞれの想いをもって関わっているかと思いますが、その一つに、「生徒や選手が部活動を通して成長し、その成長の証として試合や競技大会でその成果を発揮できること」にあるのではないかと思います。そのように考えた時、ただ単に競技成績が出ることだけではなく、「物事への取り組み方」を部活動や競技へ向き合う中で学び、その成果が競技成績に表れる、と考えると、部活動は、競技成績を出すだけではなくその後の様々な事柄への向き合い方取り組み方へも活かせる体験であることが必要と考えることができます。
そのように考えたときに、大切にしたいことは「生徒・選手が主体的に、自分で自分の課題を考え、その課題を解決するために練習を工夫していく姿勢」ではないかと思います。
この記事では、実際の悩みの声に基づき、「指導における悩み」を分類して整理しました。また、それぞれの悩みに対して、「答えを伝える」のではなく、「一緒に問いを持ち、一緒に考える」姿勢という前提で、先生や指導者の役割を考えたときの「考え方」や「対処法」もあわせて紹介していきます。
1. 指導そのものへの不安(経験不足・正解が分からない)
新しく顧問になった方や競技未経験の先生がもっとも感じやすいのが、「どう教えればよいかわからない」という不安です。技術や戦術の知識に自信が持てず、部活指導そのものにプレッシャーを感じてしまう方も少なくありません。
よくある声:
- 「部活の指導方法がわからない。とりあえず続けているけど、本当に意味があるのか不安」
- 「生徒に『なぜこの練習やるの?』と聞かれて説明できず、言葉に詰まった」
- 「何を教えたら良いかわからず、試合ばかりやってしまう」
主な悩み:
- 練習メニューの目的がわからない/効果に自信がない
- 成果が見えず、手応えがない
- 競技経験がなく、フォームや戦術が教えられない
- 指導内容が古くなっていないか心配
- 試合後にどう振り返ればいいのかわからない
考え方・対処法:
技術や知識の不足を悩むより、「生徒と一緒に考える姿勢」を大切にしましょう。「何が一番課題だと思うか?」「なぜこの練習をやるのか?」「この練習の目的・ゴールは何か?」「もしうまくいかない時どうしたらよいか?」を一緒に問い、考えながら、取り組みましょう。
💡「問い」をベースにした指導については、こちらの記事も参考にしてください:
👉「問いと観察から始める技術指導──経験がなくてもできる“考える指導”のすすめ
2. 練習メニューの作成に困る
部活動の中で日々の練習を考えることは、非常に大きな負担です。特に授業との両立が必要な先生方にとって、メニューを考える時間が取れず、前年の繰り返しになってしまうこともあります。
よくある声:
- 「自分でメニューを考えようとすると、時間ばかりかかる」
- 「強豪校の練習を真似しても、うちの生徒には難しすぎる」
主な悩み:
- 限られた時間・人数・スペースでどう練習すればいいかわからない
- レベル差があるチーム内で全員に合う練習を作るのが難しい
- 毎回同じようなメニューになり、生徒が飽きてしまう
- 「今日は何をやらせればいいのか」毎回悩んでしまう
考え方・対処法:
「練習の目的」から逆算する思考を取り入れましょう。生徒が「何が課題だと思っているか」を明確にし、それに対して段階的に練習を構成していくと、少しずつ変化がつけられます。できるだけ小さなテーマから始めて、変化や成長を感じやすくすると、生徒がモチベーションを保ちやすく取り組むことができます。
💡練習メニューの考え方については、こちらの記事も参考にしてください:
👉練習メニューが思いつかないときに大事な“問い”と“積み重ね”の視点
👉結果が出る人の練習は何が違うのか?
3. モチベーション管理ができない
指導中、生徒の表情や態度に反応がないと「やる気がないのでは」と感じてしまうことがあります。声かけに対して反応が薄いと、ますます声かけが難しくなるという悪循環に陥ることも。
よくある声:
- 「やる気がない生徒にどう接すればいいかわからない」
- 「怒っても響かない、褒めても効果が続かない」
主な悩み:
- 生徒のやる気が感じられず、どう関わればいいかわからない
- 上達しないことで生徒が落ち込み、練習の雰囲気が悪くなる
- 褒め方・叱り方が難しく、何を言っても反応が薄い
- 保護者や他の先生からの目が気になって声かけに迷いがある
考え方・対処法:
「できた」と思う体験があると、少しずつモチベーションはあがっていきます。練習メニューを工夫し、スモールステップでの目標設定や、簡単な目標から少しずつ難易度をあげるような練習の組み立てを行い、「できた!」「クリアできた!」という体験ができるようにしてみましょう。
4. 人間関係・チーム運営の悩み
チーム内の雰囲気や人間関係は、競技力の向上以前に、練習や活動の土台となる重要な要素です。学年間の壁や上下関係、部員間の対立など、技術指導とは異なるストレスが生まれやすい場面です。
よくある声:
- 「学年が違うとどうしても壁ができる」
- 「チームとしてのまとまりがない」
主な悩み:
- キャプテンやリーダーがうまく機能しない
- 部員間の雰囲気が悪い/対立があるが対応が難しい
- 学年間の上下関係がギスギスしている
- 練習以外の生活面(遅刻・言動など)での指導に迷う
考え方・対処法:
部活動で起こるチームでの課題は、「公平さ」「競技の強さ」「上下関係」等の要素が影響してきます。たとえば、上手な選手が逸脱した行動を取る、といったことがあると、「公平さ」が無いと感じて不満を感じる生徒が出てくることがあります。一つ一つの課題が起きたときに、そのチームとしてどのような考え方で運営するのか、といったことが試されている、とも言えるでしょう。もちろんチームそれぞれの考え方として、「強いことを重視する」チームもあって良いと思いますし、「公平さを重視する」チームがあっても良いと思いますが、その方針が状況によって変わってしまうことはできるだけ避けたいところです。理想としては、そのチームの方針を明確に示し、その方針に賛同した生徒・選手が部活動に参加する、という手順を踏めると良いと思います。
5. 育成の方向性に迷う
「チームとして試合で勝てる選手を中心に育てるのか、あるいはこれからの選手を中心に育てるのか」「卒業後も見据えた指導をするのか、それとも在学中に成果を出すことを重視するのか」──このように、育成の軸に迷う先生も少なくありません。特に、成績や実績が求められる場面では、短期的な結果を優先すべきか、長期的な成長を見据えるかで悩みが生まれます。
よくある声:
- 「強くするのが先か、育てるのが先か分からない」
- 「卒業後に役立つ力をどう育てればいいのか悩む」
主な悩み:
- どの選手を中心に育てるべきか迷う
- 今勝てるチームを目指すか、先を見据えて育成するかで揺れる
- 部活が進路にどうつながるかが見えない
考え方・対処法:
部活動で生徒が一所懸命に取り組んでいるからこそ、「試合に勝って喜ばせてあげたい」という気持ちは、多くの先生が持っているものだと思います。しかし、生徒自身は、長い視点で取り組んでいる、というよりかは「目の前の勝利」を目指す存在であるからこそ、先生や指導者こそがより長い視点も併せ持つことが大切ではないでしょうか。
チームの中では、一人ひとりの部員がどう関わっているかによって、全体の雰囲気や文化がつくられていきます。だからこそ、全員が「自分もチームに関わっている」と感じられるような関係づくりが重要です。たとえ試合に出ない選手であっても、「自分の関わりがチームに影響している」と実感できることが、主体性や責任感の芽生えにつながります。
また、成長の可能性は環境や条件に左右されすぎるものではありません。工夫次第で、どのような選手でも成長できる道はあります。「試合で勝てる選手」だけでなく、「いま発展途上の選手」も、それぞれが自分の課題に向き合い、工夫して取り組めるようにするために、どのようにしたらよいか、サポートする姿勢が指導者には求められます。
💡「個」と「チーム」のバランスや考え方については、こちらの記事も参考にしてください:
👉「個とチーム」をつなぐ練習づくり
6. 試合・大会に向けた準備と対応
指導経験が浅い先生ほど、「試合の仕上げ方がわからない」「試合中にどう関わればいいかわからない」といった不安を感じやすいものです。選手も不安な中、指導者自身が落ち着かない状態だと、不安が伝播してしまいます。
よくある声:
- 「試合になると選手も自分もバタバタしてしまう」
- 「もっと落ち着いて対応したいが、準備の仕方が分からない」
主な悩み:
- 試合前の過ごし方や仕上げ方がわからない
- 戦術やフォーメーションの確認が曖昧なまま試合を迎えてしまう
- 大会当日の声かけや采配に自信が持てない
考え方・対処法:
試合は「勝ち負けを決める本番」という印象が強いですが、実は日々の練習でどれだけ変化・成長できるかで、試合の結果は決まってきます。そのように考えると、試合が近いからと言って、試合に向けて何か特別なことをするのではなく、日々の取り組みそのものを見直し、どれだけ工夫と改善を積み重ねていくかが大切ではないでしょうか。
そして、試合を「評価の場」ではなく「実践と学びの場」と捉え、「試合でどこまで試せるか」「どんな状態で臨むか」を選手と一緒に言語化してみましょう。また、当日に慌てて声かけを工夫するのではなく、事前に「どういう声かけが力になるか」「試合前にどんな雰囲気をつくりたいか」なども生徒と話し合っておくと良いでしょう。
試合の準備とは、当日の段取りだけではなく、「本番で慌てない状態をつくること」。そのために、練習段階から実戦を想定した問いかけや振り返りを積み重ねておくことが、選手の自信と落ち着きを育てることにつながります。
7. 評価・保護者対応の難しさ
「自分の指導が正しいのか自信がない中での評価」や、「保護者からの期待や圧」に対して不安を感じる先生も少なくありません。実力と努力、成長と結果、評価軸のバランスは特に難しい課題です。
よくある声:
- 「公平に評価しているつもりでも、不満が出てしまう」
- 「保護者から『うちの子を見てくれない』と言われる」
主な悩み:
- 実力と努力、どちらを優先して評価するか悩む
- 保護者の期待や要望にどう応えるか迷う
- 方針の説明や情報共有に手間がかかる
- 「評価されすぎ」「関わりすぎ」への不安
考え方・対処法:
成長には個人差があり、それぞれに課題があり、それぞれに成長するタイミングがあるものではないでしょうか。誰かと比べて良い悪いや優劣を判断するのではなく、今の取り組みが本人にとってどんな意味を持ち、どこに向かっているかを見つめ、その点を共有するような視点を持つことも一つだと思います。
指導の軸を持ち、「こうありたい」と思う選手像や成長の方向性を言語化して伝えることが、信頼の土台になります。特に保護者対応では、指導の理念や方針を日常的に発信し、「見えていない場面での取り組み」も含めて、生徒の努力を伝えていくことが、誤解を防ぎ関係性を築く鍵となります。
8. 日々の時間確保・労力の負担
多忙な先生にとって、部活動が心身の負担になるケースは非常に多くあります。教科指導や家庭との両立、業務の多さにより、「このまま続けられるのか」と感じる瞬間も少なくありません。
よくある声:
- 「部活が生活の中心になりすぎてしんどい」
- 「教科の仕事に集中したいけど、部活が優先されがち」
主な悩み:
- 授業・会議・家庭との両立が難しい
- 練習後の片付け・送迎対応・報告書類などの業務が重い
- 1人で全部抱える状態に限界を感じている
考え方・対処法:
生徒に「自分の課題を自分で捉え、主体的に取り組む」姿勢を求めるなら、先生自身も「すべてを自分一人で抱え込まなくていい」という選択をすることが大切ではないでしょうか。部活動のすべてを一人で背負う必要はありません。保護者の協力や、他の教員、外部指導者の力を借りることも重要な工夫です。それは「甘え」ではなく、教育的にも意味のある判断です。
また、練習やチームの運営においても、生徒たちが自分たちで課題を考え、チームのために何ができるかを話し合い、分担し合う文化を育てることが、先生の負担を軽減すると同時に、生徒たちの主体性を育てるきっかけにもなります。先生が疲弊してしまっては、良い指導も続けることができません。自分自身の健康と心の余裕を大切にしながら、チームで支え合える仕組みをつくっていきましょう。
おわりに
部活動の指導に正解はありません。だからこそ、「うまくいかない」と感じることがあっても、それは指導者としての失敗ではなく、次のステップへのヒントになります。
本記事では、よくある悩みを8つに分けてご紹介しましたが、共通して大切にしたいのは、「一人で抱え込まず、生徒と一緒に考えていくこと」です。
生徒に主体性を求めるなら、指導者も「支え合う姿勢」を大切に。信頼や成長は、一方的な指導ではなく、対話と共感の中から生まれます。
生徒たちとともに悩み、考え、歩む過程こそが、部活動のもっとも価値ある時間です。この記事が、その一助となれば幸いです。
