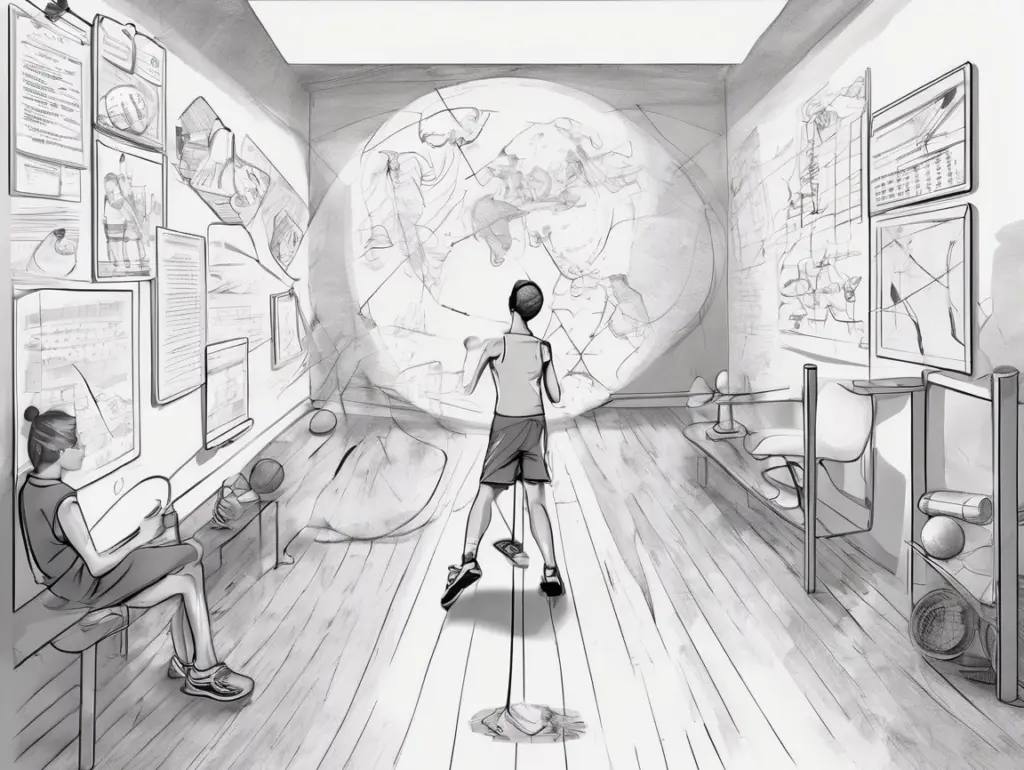
どれだけ続けても伸びない。努力しているのに報われない。練習しているのに成果が出ない。そんなふうに感じる時期は、誰にでもあるものです。
毎日部活に行き、指導も真面目に聞き、きちんと取り組んでいるのに、成績が伸びない。プレーが良くならない。周りとの差が縮まらない。
「がんばってるのに…なぜ?」
そんなふうに悩んでいる人が、いま多くいます。結果が出ないとき、つい「もっとがんばろう」「継続が大事」と自分を奮い立たせたくなりますし、そう言われてきた人も多いでしょう。でも、そうした言葉だけでは前に進めないかもしれません。
成果が出ないなら、まず「原因」を問い直そう
「続けていればそのうち伸びる」「努力していれば結果はついてくる」と私たちはつい信じたくなります。実際、多くの人がそう言われ、励まされてきたことでしょう。また、そう信じることで希望を持ってきた面があるからではないでしょうか。
ですが、結果が出ていないということは、「本当の原因」に取り組めていない可能性があります。うまくいっていない結果には必ずその原因があります。もちろんそうした原因を改善するべく取り組んでいると思いますが、その原因が異なっていたり、原因の原因が存在したり、複数の要因が絡み合っているとしたら、いかがでしょうか。今の取り組みでは十分に効果が出ないかもしれません。
だからこそ、「なぜ結果が出ていないのか?」「どんな要素が影響しているのか?」を問い直すことが、最初の一歩として必要になります。
なぜ「本当の原因」が見つからないのか?
結果が出ていないとき、私たちは原因を問い直したり、やり方を工夫するのではなく、『努力が足りない』『もう少し続けてみよう』と思ってしまうことがあります。本来は、原因が何かを振り返ったり、やり方を工夫する必要があるのに、なぜそう考えてしまうのでしょうか。
そこには、以下のような考えが存在します。
- 今までの努力を否定されたくない、過去の自分を守りたい
- 新しい取り組みに対する不安や恐れがある、失敗したくない
- 変化よりも、慣れている安心感を優先してしまう
- 「続けること」が努力であり、正しいと信じてきた
ここまで努力をして、続けてきたあなたは、自分のやってきたことへの自負があり、それがあなたの自信にもつながっている部分があるのかもしれません。たしかに、今の自分が存在するのは、これまでの積み上げてきたものがあるからこそです。だからこそこれまでのやり方で取り組めば成果が出るだろうとも思えるものですが、もしもうまくいっていないとしたら『続けたら伸びる』『がんばったら成果が出る』という前提と向き合う必要があるかもしれません。
不安定な土台には高く積み上げられない
スポーツにおける成果や成功は、様々な要素が積み上がっているものです。今のあなたは、これまでの積み重ねの成果でできあがっています。でもその積み重ねの中身を詳しく見たとき、もしも土台が不安定な部分があり、それが今うまくいっていない結果につながっているとしたらどうでしょうか。
このように不安定に積み重ねられたものに、さらに無理やり高く積み上げようとしても積み上げられません。さらに高く積み上げたものにするためには、一度積み重ねたものを壊して、再構築し直す必要があります。しかし、これまで積み上げてきたものが壊れることには恐れが伴います。「せっかくここまでやってきたのに」「もしかしたら今度の試合でうまくいかないかも」「また一からやり直しか…」と感じてしまうことから、「続けたら伸びるはず」「努力したら報われるはず」と思いたいのかもしれません。でも、もしも不安定な土台の上にこれまで積み重ねてきたのなら、もうこれ以上は積み重ねられません。
原因を解きほぐす
まず、実際に取り組みを始めるかどうかは一旦脇において、うまくいっていない原因がどこにあるのか、「原因の原因」や「複数の原因」が絡み合っていることがないかどうか、問い直しながら振り返ってみましょう。
たとえば、フォームが崩れる原因がタイミングのズレだとしても、そのタイミングのズレは「ボールとの距離感」や「予測の精度」が影響しているかもしれません。さらにその背景には「相手の動きを見ていない」という観察力の問題があるかもしれないのです。
まずは原因を解きほぐし、本当の原因がどこにあるのか、これまで積み重ねたもののどこを修正する必要があるのか、どこを積み直す必要があるのかを明らかにしましょう。
原因を解きほぐす、原因と結果の考え方についてはこちらも参考にしてください
👉️上達する人が実践する原因と結果の考え方
積み上げ直すことへの不安と向き合う
原因を解きほぐし、明らかにしたとしても、これまでのやり方や取り組み方を変えたり、積み上げ直すことには不安が伴うものです。「変えなきゃいけないのはわかっているけれど、今までの努力が無駄になるのではないか」「今のままでもう少しで成果が出るのではないか」といった気持ちがよぎるかもしれません。
そうしたときに大切なのは、「変えること」は過去の努力を否定することではなく、より深く理解し直し、未来に活かす行為だということです。いま感じている不安は、過去を否定されることへの恐れや、先が見えないことによる不安であることが多いのです。
そこで役立つのが、「段階的に変える」という考え方です。すべてを一気に変える必要はなく、小さな部分から変化を始めることで、「これならできる」「思ったより不安ではない」といった感覚が得られることがあります。さらに、仲間や指導者と一緒に振り返ったり、新しい取り組みを共有することで、不安を安心に変えていくことができるのです。
「不安があるからダメ」なのではなく、「不安があるからこそ丁寧に変える」ことが大切だと捉えてみましょう。
原因に取り組む「練習」を設計する
原因に対する気付きが得られたら、今度はそれを練習で取り組んでいきましょう。練習で「ただ続ける」「ただ練習する」だけでは、原因が改善されず成長にはつながりません。
何をもって改善できているのか明確に取り組む
練習をより意味あるものにするためには、まずその練習の目的と難易度を整理し、どこまでできたら成功で、どこからが失敗なのかという「基準」を明確に設定することが大切です。何のためにこの練習をしているのか?
- いまの取り組みはどこを改善するためなのか?
- その改善がどういう結果につながるのか?
- 何がどうなると原因が改善できているのか?
- 改善するためにどのように取り組むのか?
これらの問いを自分自身に投げかけながら、練習を”自分のもの”として捉え直していくことが大切です。
💡「成功の基準を明確にする」練習の作り方については、こちらの記事も参考にしてください:
→結果が出る人の練習は何が違うのか?
スモールステップで練習を設計する
もしその取り組んでいる課題がうまく改善されない場合は、さらにスモールステップに分解し、より簡単に実践できる形に変えていく必要があります。たとえば、「ボールへの反応を早くする」という課題に取り組み、うまく改善されないとしたら、なぜ反応が早くならないのかを問い、「反応を早くする」をさらに細かい要素に分けて1つつず取り組んでみましょう。例えば「ボールの質を見抜く」「ボールを見抜くための準備を整えておく」など、段階的に実践しやすくすることで、本当の原因を見つけると同時に、小さな成功体験を積み重ねられる構造にするのです。
こうした練習設計ができれば、「続けること」そのものが成長につながる感覚を得やすくなり、日々の取り組みにも前向きな意味を持たせることができるでしょう。
スモールステップで取り組むための練習の設計についてはこちらも参考にしてください
👉️「できない」を「できる」に変える練習法
まとめ
「続けているのに伸びない」「努力が実らない」と感じるときこそ、自分の練習や取り組みを”問い直すチャンス”です。
成果が出ないのには必ず理由があります。そして、その原因に目を向けることを恐れず、丁寧に解きほぐし、小さく試し、積み直していくプロセスこそが成長の本質です。
努力は無駄にはなりません。ただ、その方向や積み方を見直すことによって、初めて成果に結びつく努力へと変えていくことができるのです。
練習において視点を変えながら振り返る方法についてはこちらも参考にしてください
👉️結果を変える振り返りの技術
