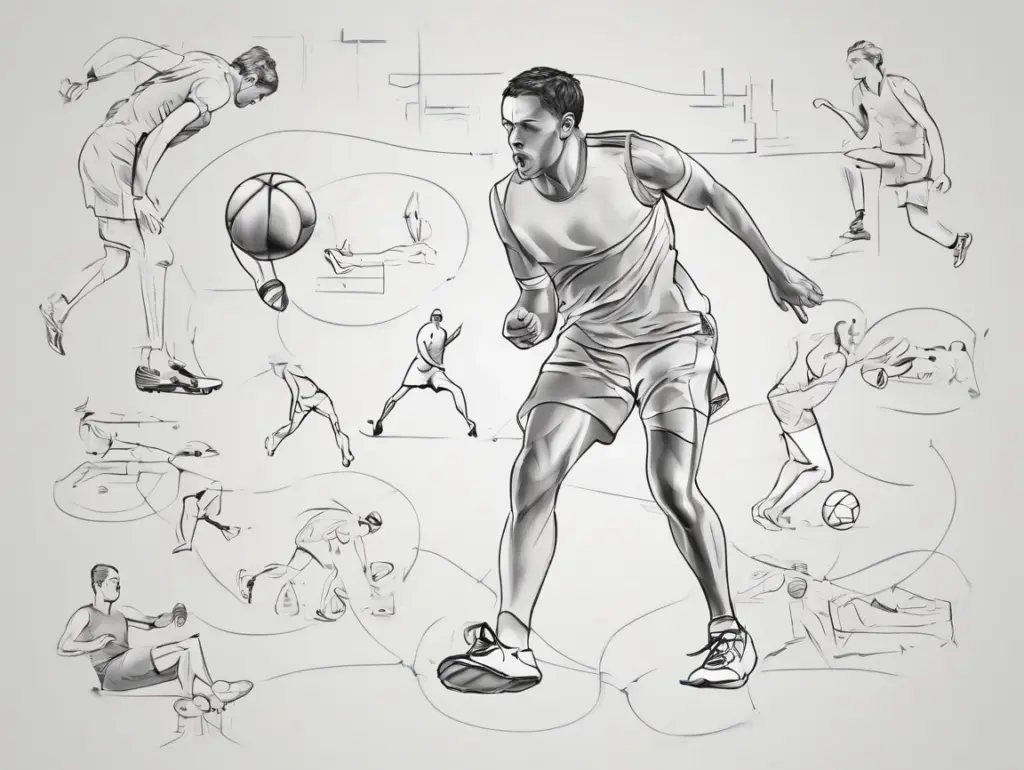
スポーツの練習や試合で「うまくいかない」「思った通りに動けない」という経験は誰にでもあります。そのとき、多くの人はすぐに「結果」に目を向けます。点が取れなかった、ミスをした、勝てなかった…。もちろん結果は大切ですが、そこから学びを得るためには「原因」を探ることが欠かせません。しかも、その原因は一つではなく、複数が重なり合い、さらに「原因の原因」といった連鎖的な背景が存在するのです。
結果から原因を探す第一歩
結果が出なかったときに大切なのは、「なぜそうなったのか」を具体的に考えることです。たとえばテニスの試合でリターンが入らなかったとします。このとき「リターンが下手だから」で終わらせてしまうと、解決にはつながりません。打点の位置がずれていたのか、タイミングが遅れたのか、構えが遅れたのか。まずは一つひとつ要素を分解してみることが重要です。
このように原因を誰しもが考えると思うのですが、なぜそうした取り組みで改善されていかないのでしょう。
それは、多くの人が「原因はこれだ」と早い段階で決めつけてしまうからです。一つの答えに飛びつくことで、それ以外の可能性を探る視点が失われてしまいます。
例えば「フットワークが遅れているのは反応が遅いからだ」と決めつけて反応練習ばかりしていたが、実際には構えが遅れていて、その構えの遅れは相手を十分に観察していないことが原因だった、ということもあります。
原因が一つだと信じて取り組むことで、間違った修正に時間をかけてしまい、結果的に成長の停滞や自信の喪失を招くことがあります。だからこそ「他にもあるかもしれない」と考える姿勢が重要であり、そうした行き詰まりを避けるためには、はじめから「原因は複数あるかもしれない」と考える視点が重要です。
例えば、リターンが入らないのも、単にスイングの問題ではなく、相手のサーブをよく見られていない、フットワークの準備が遅い、といった要素が組み合わさっていることがあります。「体の動き」「認知」「判断」等がそれぞれに影響し合って結果が生まれています。表面的な一因に片付けたり、一つに限定して考えてしまうと、根本的な改善を見逃してしまうのです。
原因の原因を掘り下げる
さらに、原因だと考えたことも、実はもっと奥深くに本当の原因があるかもしれません。たとえば「フットワークが遅れた」という原因があったとします。そこで「反応が遅かった」とだけ判断して練習に取り組んでも、うまく改善しないことがあります。
たとえば反応トレーニングを繰り返しても改善されなかった場合、実はその前段階で構えが間に合っておらず、そもそも動き出しの準備ができていなかった、という背景があることもあります。さらにその原因をたどると、「相手の打つコースを想定できていなかった」「次の展開を考えすぎて初動が遅れた」といった要素が見えてくるのです。
このように、原因は複数の場合や原因の原因がある場合もあるので、本当の原因にまで遡れなければ、必要な改善がされず、表面的な修正に終始してしまいます。だからこそ、掘り下げていくことで、本質的な改善点にたどり着けるのです。
探す視点を持つことの難しさ
曖昧な言葉で片付けてしまう
多くの選手は、結果が出ないと「メンタルが弱い」「集中力が足りない」といった曖昧な言葉で片付けてしまいます。たとえば「ミスが多いのは集中力が足りないからだ」と判断して、集中力を高めるための音楽やルーティンばかりに気を取られてしまうケースがあります。しかし実際には「技術的に不安があり、その不安から気が散っていた」など、別の要因が隠れていることが多いのです。
このように曖昧な言葉で片付けてしまうと、具体的に何をすればよいかが見えなくなり、的外れな努力を続けることになります。それでは成果は上がらず、自己効力感を失っていく恐れすらあります。さらに、あいまいな改善点は自分がそれをできているかどうかも不明確になり、どれだけ意識しても終わりがないので、本当は他の原因があるにも関わらず、誤った原因を意識し続けることになってしまいます。
こうした事態を避けるためには、「その言葉はどの具体的な動きや認知、判断とつながっているのか?」を問い直すことが必要です。プレーの中での身体の使い方、見ている情報、選んでいる行動にまで落とし込めてはじめて、自分が実際に取り組むべき具体的な改善点が見えてきます。そして、意識していることができているかどうかが明確にわかるかどうかも合わせて確認しましょう。自分なりの具体的な仮説を立てて検証することが、曖昧さを超えて本質に近づくための鍵となります。
よく言われていることが原因だと考えてしまう
原因を探そうとしたとき、誰もが最初に思い浮かべるのは「よく耳にする言葉」や「一般的に正しそうな知識」です。たとえば「メンタルが弱いからうまくいかない」「集中力が続かないからミスが増える」といったフレーズです。もちろん、これらが一因である場合もありますが、そうした一般論をそのまま“原因”と受け取ってしまうと、本質的な改善にはつながりません。
たとえば、ある選手が「大事な場面で緊張してサーブミスをする」と相談したとします。すると多くの場合「メンタルを強くしよう」という方向で取り組みが進みます。しかし、実際には「緊張したときに手首が固まりやすいフォームになっている」「リズムが速くなってトスの高さがぶれる」といった、技術的な要素が絡んでいることもあるのです。これらを見逃してしまうと、メンタルトレーニングだけに取り組んでもミスは減りません。
このような誤ったアプローチを避けるためには、「その言葉が、自分の動きやプレーのどの部分に結びついているのか?」を問い直すことが必要です。一般論をうのみにせず、自分のプレーの具体的な場面や動きに照らして検証する姿勢が求められます。
一つの原因に固執する
一つの原因を見つけたからといって安心しないようにしましょう。たとえば、「ラリーでミスが続くのはフットワークが課題だ」と決めつけて、フットワークの練習だけを繰り返したとします。しかし、実際には他にも原因がある場合もあります。一つの原因に固執すると、他の重要な要因を見逃してしまい、練習の方向性を誤ったまま時間だけが過ぎてしまいます。その結果、成果が出ずに自信を失ったり、「自分には才能がないのでは」といった誤った自己評価につながることもあります。
そうした事態を防ぐには、最初に思いついた原因を出発点としつつも、「他に考えられることはないか」「これが本当に原因か」と常に問い直すことが重要です。認知・判断・動きといった視点に分けて多角的に見直すことで、本当の原因にたどり着ける可能性が高まります。そして、取り組みの結果として「本当にそれで最終的に起こしたい変化が生まれているか」を確認することも大切です。結果が伴っていないなら、さらに別の原因がある可能性を視野に入れて見直していく必要があります。
練習で因果関係を考えながら取り組む
練習や試合において、常に原因を探索する習慣を持ちましょう。たとえば次のように整理します。
- 結果:サーブがネットにかかった
- 原因:打点が低かった
- 原因の原因:トスが低いことに気づけていなかった
- 原因の原因の原因:ボールの高さを意識しながらトスを見れていなかった
このように分解していくと、改善のために取り組むべき最初のポイントが明確になります。
例えば、実際の練習ではこのように実践してみましょう。
- 仮説を立てて試す
ミスが起きたときに「打点が遅れたかもしれない」と仮説を立てて、次の1球で意識的に打点を早くしながら取り組みます。 - 取り組みと結果を振り返る
仮説を試した時に、「仮説通りに試せたか」「仮説通りに試した時に変化が起きていたか」を確かめます。仮説通りに試すことができていないときは、仮説として設定した原因があいまいであったりする場合があります。仮説通りに試せた時に、どんな場面で変化が出たか、そしてどんな場面で変化が出ていないかを記録しておくと、原因の傾向が見えてきます。練習後に振り返り、次のテーマ設定にもつなげられます。 - 原因を探索する
原因を探索するときには、時間や場所の要素を切り分けて整理してみましょう。課題が起こっている時間から少しずつ時間を遡り、それぞれの時間帯で課題につながっている原因を整理していきます。また、動きに関しては、動きを小さく分解して、原因となっている部分を特定するようにしてみましょう。例えばテニスであれば、「相手が打つ時にスプリットステップを行う」「相手が打った直後にボールの勢いを見抜いておおよその軌道を予測する」「移動を開始する」「バウンドするまでに移動を終えて構えを作る」「構えたあとにバウンドを見て打点のズレがある場合気付けるようにする」といったかたちで分けることができます。各競技にもよりますが、切り分けるときには、時間であれば1秒よりも短い単位で、動きであれば各関節単位で切り分けて観察し、分解できると良いと思います。
成長を生む「原因探し」の姿勢
結果を見て一喜一憂するのではなく、原因を探り、その原因の原因にこそ成長のヒントがあります。原因は一つではなく、複数が絡み合い、さらにその背景に原因の原因があります。丁寧に掘り下げていくことがあなたを次のステージへと導いてくれるでしょう。
また、原因を探る姿勢は、単なる問題解決にとどまりません。それは「自分を深く知る」という自己探求でもあります。なぜ自分はその場面で動けなかったのか。どのような思考や感情が影響していたのか。その理解が進むほど、プレーは安定し、再現性が高まります。
成長する人がどのように練習を設計しているか、その考え方についてはこちらも参考にしてください。
👉️成長する選手の練習の秘密
