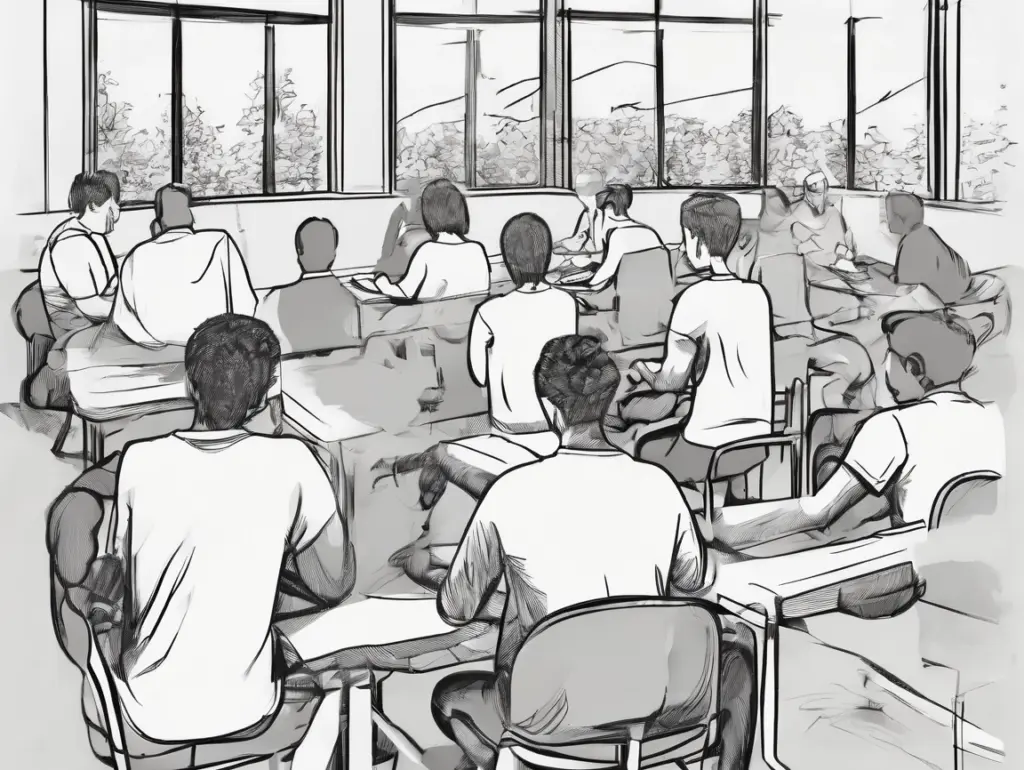
どれだけ練習しても思うように成果が出ない。
努力を続けているのに「自分は成長しているのか?」と不安になる。
そんな経験をしたことはないでしょうか。
これはスポーツに限った話ではありません。勉強でも仕事でも、「時間をかけて取り組んでいるのに、前に進んでいない」と感じる瞬間があります。多くの人は、もっと努力しなければと考えます。しかし、その努力が空回りしていることに気づけなければ、いくら積み重ねても結果は変わりません。
では、努力を「変化を生む努力」にするにはどうすればいいのでしょうか。
その鍵になるのが「観察」です。
努力の質は観察から始まる
努力という言葉は、とかく「量」と結びつけて語られがちです。しかし本当に重要なのは「質」を伴った「量」であり、「質」が伴わない「量」は逆効果を及ぼす場合もあります。そしてその質を左右するのが、「観察」です。
上達や改善を目指すとき、「理想のフォーム」や「できるようになりたい姿」「アドバイス通りの動き」に意識を向けがちです。しかし、それは「今の自分」ではない姿を追い求めることであり、意識が「今の自分」から離れたものになってしまいます。追い求めることは必要ですが、大切なのは、今の自分を丁寧に観察し、今の自分がどう変化することが必要なのかを明らかにすることです。観察が行われずに理想ばかり追いかけると、今の自分がどのような状態か理解できないまま理想の姿を思い描くことになり、何が原因でうまくいっていないのかが曖昧なままになり、どれだけ練習しても成果に結びつきません。
もしかしたら、「自分のことくらい自分はよくわかっている」と思うかもしれません。しかし、本当にそうでしょうか。たとえば、
- いま、理想とする動きができないのは、自分の体のどこがどのようになっているからでしょうか?
- プレッシャーがかかったとき、どんな思考の癖が出ているでしょうか?どんな不安や恐れがありますか?それはどのようなことを想像していますか?それによって体のどこがどのようにいつもと違う動きになっていますか?
- ミスや失敗をしたとき、それはうまくいったときとどう違ったのでしょうか?それはなぜ発生してしまったのでしょうか?それは発生しないように注意深く取り組んだのにも関わらず、発生してしまったのはなぜでしょうか?
たとえば、こうした問いに明確に答えられないとすれば、それは「観察」がまだ曖昧なままであるということかもしれません。
観察をして、今の自分に何が起きているのかを把握し、「いつ、どのように動き、気づき、考え、判断しているのか」を具体的にすることで、そこに改善を施していくことができます。
観察は無意識を意識化する入口
上達とは、できなかったことを「無意識にできる」ように変えていくことでもあります。試合では、多くのことを判断し、処理していく必要がありますが、それらのすべてを意識しながら処理することはできませんし、瞬時に的確に動けるように、判断できるようにする必要があります。だからこそ、体には、自動的に発揮される「良いプログラム」が組み込まれている必要があります。技術を習得するプロセスは、「無意識に行っているプログラム」を一度意識に引き上げ、より良いプログラムに修正し、再び新しい無意識に落とし込む作業だと言えます。
観察はその最初の入口です。普段は気づかなかった無意識のプログラムである動きや感覚、判断の癖を観察によって意識化し、そこで得られた気づきを繰り返し練習して、より良いプログラムに修正することで、新しいプログラムを無意識に組み込んでいくことができます。
このプロセスを経ることで、試合の場面でも安定して力を発揮できるようになります。つまり観察は、練習と本番をつなぐ架け橋でもあるのです。
観察は自己との対話
試合における焦りや不安は、ミスをした直後に「もっとこうしておけば」考えたり、勝ちたい気持ちが強すぎて自分の手に入れたい未来を見て焦った決断をするように、意識が過去や未来に飛んでいるときに起こります。そんなときに必要なのは、焦りや不安を否定せず、「そう感じている今の自分」を観察することです。観察を行うことを通して意識を「今」に向けていくことができるので、心を整えていくことができるのです。
しかし、焦りや不安を感じていることを否定せず、観察をして今に意識を戻す、と頭で考えて、できるものでしょうか。スポーツの様々な場面で表れる感情や体の動きは、自分の思いや意図が映し出された鏡のようなものでもあります。これまでの自分の判断の癖、反応のパターン、過去の経験に起因する思い込みなどが形となって動きや感情に表れている、ということもできるでしょう。そのように考えると、勝負に挑む、ということは、自分の存在が問われるような体験でもあります。勝負の場において、どんなに自分を取り繕おうとしても、できないことはできないこととして露呈し、培ってきたことはできることとして表現されます。それは、「自分がなぜこの競技に取り組んでいるのか」「どのような価値観で、取り組み方で向き合ってきたのか」という問いを突きつけられることでもあります。
感情が表れ出た時に、自分に都合よく焦りや不安を取り除きたいと思って観察をしようとしても、そこにいる「自分にとって都合の悪いものは遠ざけたい」という自分がいることからは目をそらし、根本の自分を観察することはできていないので、どこかで焦りや不安を抱えながら戦うことになります。つまり「今の感情を認める」ということは、自分の中にいる本当は見たくない、弱い自分、受け入れたくない自分をも含めて観察する、ということでもあります。偏った見方で見る都合の良い自分だけではなく、そのままのすべての自分を見つめることが観察であり、そのように観察をすることを通して見つけた今の自分で戦うことで、そのときの自分にできる限りの精一杯の力を出し尽くすことに集中することができます.
『ミスが続くと気持ちが切れる・焦る』という状況に対して、どのように観察から想定へ、そして再現練習へとつなげる流れについて詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。
👉️ミスを引きずる人と切り替えられる人の小さな違い
緊張したときに、体や呼吸の観察から心を整えていくアプローチについては、こちらの記事も参考にしてください。
👉️“ここぞの場面”で落ち着ける人の頭の中
まとめ
「努力しているのに前に進めない」と焦りをへの感じたときこそ、観察によって“今の自分”を正確に捉え、必要な一歩を具体化してみましょう。そこから生まれる気づきと修正の積み重ねが、練習を変化を生む営みに変えていきます。
