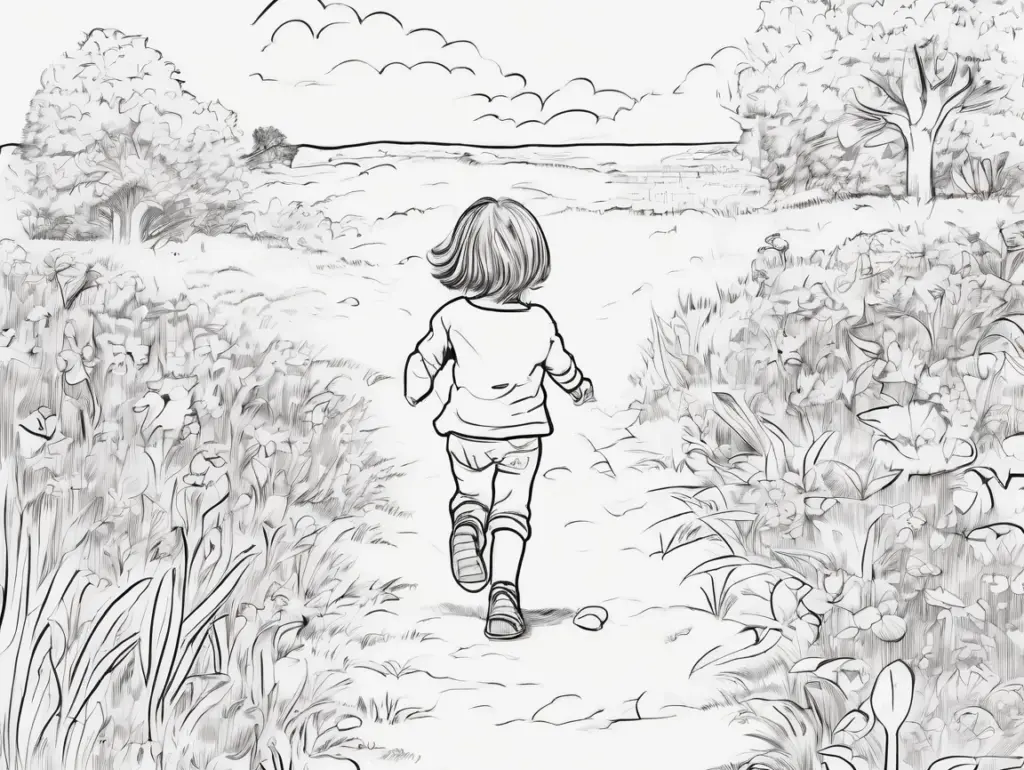
子どもが「自信がない」と感じている様子を見ると、大人としては何とかしてあげたいと思うものです。自信があれば、もっと挑戦できるのではないか、もっと楽しめるのではないか、そんな思いが自然に湧いてくるのは当然です。
しかし、そもそも「自信」とは何でしょうか? この問いかけから始めて、自信について考えてみたいと思います。
「自信」の背景にあるもの
多くの場面で「子どもに自信を持たせる方法」として紹介されているのは、「成功体験を積ませること」や「たくさん褒めること」です。もちろん、こうした「できた」体験、「成功した」体験で自信がつくことも事実です。
しかしここで考えたいのは、たしかに成功体験や褒め言葉によって一時的に自信を感じることは可能ですが、そうした「外からの評価」や「結果」によって自信を感じる体験は、評価されることや結果を求める傾向が強くなり、子どもの自らの内側で育まれる自信にはつながらなくなってしまいます。つまり、褒めることや成功体験の積み重ねが、かえって子どもの主体性や自律的な学びの意欲を削いでしまうリスクもあるのです。
「できた」「成功した」体験の前提には、何をもって「できた」「成功した」と決めているのか、という「基準」が必ず存在します。たとえば、テストで80点を取って「できた」という体験が生まれるためには、「80点」という基準が必要です。そのように考えると、仮に「できた」「成功した」という体験には、「その基準を通して判断をする」という捉え方が含まれています。そして、この「基準を通して判断する」ような捉え方は、一度「できた」「成功した」と感じても、その先には「もっとできる誰か」「さらに上の水準」を生み出します。つまり、常に自分は“まだ足りない”“まだできていない”という感覚と隣り合わせになってしまうのです。
その結果、「自信がある子」に育てたいという想いが、結果的に「自信がない」「自信が持てない」自分を見つけてしまう習慣を作る危険もあるのです。
自分はどういう基準で見ているのか?
そのように考えると、「自信がない」と捉えている前提にある「基準」を捉えることで、どのようなものの見方をしているのかが見えてきます。そうした「捉え方」に意識的になると、その「捉え方」とは異なった「基準」や「ものの見方」が存在することへの気付きにつながります。
- 何をもって「できている」「できていない」と感じているのか?
- 何と比べているのか?
- その基準は、誰が決めたものなのか?
こうした問いを重ね、自分の中に根付いている「基準」に意識的になる中で、「違った基準」「違った捉え方」で見れることへの気付きや、そうした捉え方で見た時に、同じ事柄に対しても違った見え方がされてくるかもしれません。
「できない」があるから、「できている」がある
「できる」「できない」という評価そのものが、何らかの「基準」があることによって生まれていることが見えてくると、そうした基準がなければ、「できない」は生まれない、ということも見えてきます。つまり、「できない」という状態と「できている」状態は、基準というものの見方でみた時に同時に生まれてくるものであって、「できる」と「できない」はセットになっている、ということがわかってきます。
つまり、私たちは「できない」と感じた経験があるからこそ、「できた」ときに達成感を得られ、「できない状態」がなければ、「できている状態」を実感することはできません。
「自信がない」「自信が持てない」「できていない」と感じるとき、人は不安や焦り、できればその状態を避けたい、どうにかしたいと思います。しかし、それは「できていない」ことを、誰かと比べて劣っていると感じたり、期待に応えられない自分に対して責めるように、否定的に捉えているからこそだと考えられます。「できていない」ことを、否定的に捉えるのではなく、むしろ成長するチャンスであると肯定的に捉えると、「できていない」状態は避けるような性格のものではない、ということにも気付かされます。
「できない」を「できる」に変えていくための練習の設計についてはこちらも参考にしてください。
👉️「できない」を「できる」に変える練習法
「比較」から自由になるという選択肢
一方で、そもそも自信という言葉の背景にある「基準」や「できる/できない」といった、相対的な評価の枠組みから自由になることはできないのでしょうか。
私たちの「自信」の多くは、他者との比較の中で形づくられています。それはときに励みになりますが、そうした相対的に自分の位置を確認するようなものの見方は、どれだけがんばって「できる」ようになったとしても、上には上が存在し、必ず“もっとできる誰か”が存在する、という現実にも直面することになります。
こうした姿は、なにかに取り組んでいながらも、常に心のなかで回りを見回し、自分の位置を確認するような姿を想像させます。
しかし、今取り組んでいること、例えば勉強でも、スポーツでも、遊びでも、そこで行われる「行為」はただの行為であるはずなのに、それを「基準」という捉え方を通して行うことで、「できた/できない」といった評価が生まれてきます。
一方で、同じ行為を小さい子供が没頭している様子を想像してみてください。同じことをしていても、そこには、『これにどのような意味があるか』や『できなかったらどうしよう』といった捉え方は存在せず、ただその行為行動に没頭して取り組む様子が見て取れると思います。
ということは、行為行動とそれに対する「捉え方」はそれぞれで存在していて切り離すことも可能なものであり、行為行動のみに純粋に集中して取り組む、というあり方もできることがわかります。そして、この行為行動に純粋に集中している瞬間には、「できている」ことで自信を得ている姿とは異なった、満たされた姿も見て取れるのではないでしょうか。
自分で自分を振り返る力を育む
「できていない」ことを肯定的に捉える視点が持てると、それまでの「評価」や「比較」の枠組みから少し自由になれるかもしれません。ここでは、さらに「できた/できていない」という基準を、他者から与えられたものだけでなく、自分自身で決めていくという視点も提案したいと思います。
勉強にしてもスポーツにしても、何かをできるようになるには積み重ねが欠かせません。その積み重ねは時に苦しく、変化が見えず、途中で怠けたくなることもあります。そんなときに、「自分には自信がないからダメだ」と感じてしまうこともあるでしょう。
もしこの「基準」が他者から与えられたものであれば、「なぜ頑張らなければいけないのか」が自分の中で曖昧になりがちです。そうなると、逃げたくなったり、あるいは外から見れば努力しているように見えても、内面では深く集中できておらず、ただ「頑張っている姿」を取り繕ってしまうことも起きてきます。
人は、自分という存在を、自分自身で確認したいという根源的な欲求を持っています。だからこそ、たとえ他者が設定した基準であっても、それを満たすことで「自分はできた」と感じたい、自分を肯定したいと思うのです。けれど、その基準が他者によってつくられたものである限り、「できた自分」は他者の目を通して存在する自分に過ぎません。自分で自分を確認したいという欲求は、たとえ他者基準であっても「満たしたい」と感じさせる力を持ちますが、それによって手に入るのは“他者が期待した自分”です。逃げたくなったり怠けたくなったりする弱い自分も「自分」なのですが、他者が期待した基準に当てはめると、そうした「自分」は、「自分ではない」と否定してしまうため、「自分がない」「自信もない」状態になってしまいます。つまり、他者の基準で自分を見ようとしているときは、その線より“上”にいるときだけ〈自分〉が現れ、線より“下”にいるときは〈自分〉が表れない、ということが起きます。
しかし、自分が決めた基準であれば、その基準より上であっても下であっても、そこには「自分」という存在が表れます。もちろん「できなかった」体験は痛いものですが、「自分」という存在が表れているので、そうした自分も引き受けて「なぜ届かなかったのか」「次にどう歩むのか」という一歩を踏み出すことができるのです。
つまり、他者基準であっても自分基準であっても、「できなかった」「自信が持てなかった」という体験は生まれてしまいますが、自分基準においては、その体験の中に「自分という存在」が確かに立ち現れています。自信とは、文字通り「自分を信じる」ことです。そして信じる対象となる「自分」が明らかでないと、信じることはできません。自分の姿が表れていなければ、信じようにも信じられないですし、まだ信じれる自分ではないとしても、自分という存在がそこに在ることを感じ取れていれば、歩み続けることができるのです。
自分の基準を持つためには、自分で自分を観察する視点を育むことが最初の一歩になります。そのための解説はこちらも参考にしてください。
👉️結果を変える振り返りの技術
まとめ
ここまで、自信という言葉の背景にある「基準」や「評価」「比較」といった構造を掘り下げてきました。
どのような基準で「できる/できない」と捉えているかに自覚的になること、できないことを否定せず肯定的に捉える視点、さらに比較を離れて行為そのものに没頭する姿勢、そして最後には「自分自身が自分の基準をもつこと」の意義について考察してきました。
こうした視点のどれか、というよりかは、そもそも持ち合わせていた基準も含めた複数の視点を持つことで、「自信がある/ない」といった一元的な捉え方ではなく、今の状態をより多角的に、柔軟に見つめることができるようになります。そのような複眼的なまなざしを持てるようになることが、「自信がある/ない」といった表層的な言葉に左右されず、今の自分を引き受けて歩んでいける“本当の自信”につながるのではないでしょうか。
