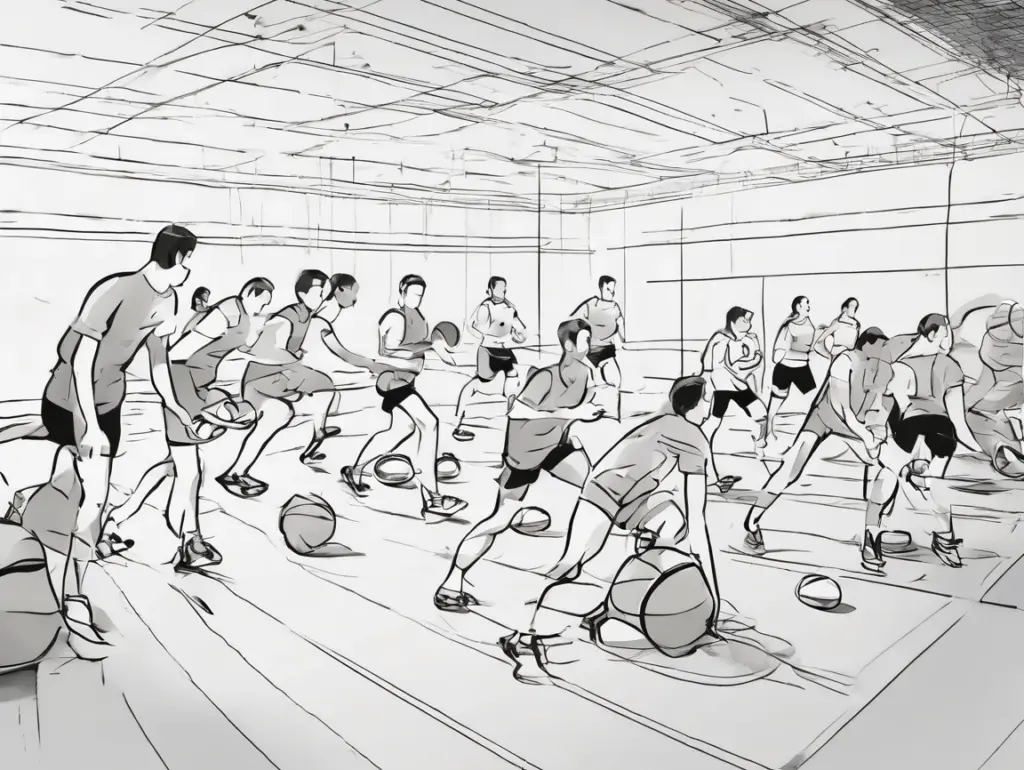
「強いチームの練習を真似すれば、自分たちも強くなれるはずだ」──そう考えて、雑誌や動画で紹介された練習メニューを取り入れたことはありませんか? あるいは有名選手がやっている練習法をそのままやってみたけれど、思ったような効果が得られなかったという経験もあるかもしれません。
ですが、すでに気づいている通り、どんなにすばらしい練習メニューでも、それをやるだけで自動的に上達するというわけではありません。大切なのは、そのメニューが「自分たちの今の課題に合っているか」、そして「効果が出ているかを観察し、調整して」取り組めているか、ということです。
この記事では、そうした視点から「本当に上達につながる練習メニューの使い方とは?」を一緒に考えていきます。他のサイトではあまり触れられない、練習の“考え方”に注目していきます。
メニューを組むときの考え方でこうしてませんか?
1. 強い学校や選手がやっているメニューを取り入れる
実績のあるチームの練習メニューを真似るのは、一見もっともらしく感じられます。しかし、そのチームの選手構成・技術レベル・指導者の意図・取り巻く環境などが違えば、同じ練習メニューでも意味合いが変わってきます。たとえば、基本的な技術が完成しているチームでは、その技術を発揮するための「走り込みを重視する練習」が重要かもしれませんが、技術的な課題を抱えるチームには合わないかもしれません。
2. マンネリ化を避けて目新しい・楽しいメニューを入れる
選手が飽きないように、変化や楽しさを求めるのは悪いことではありません。ただ、「楽しいからやる」という目的だけでは、上達につながらないこともあります。例えばリズムトレーニングを入れたとしても、それが今の課題と関係なければ、ただの気分転換で終わってしまいます。
3. 選手に任せてゲーム形式が多くなる
自主性を重んじているつもりが、実際は「考えなくても成立する練習メニュー」に流れてしまうケースがあります。ゲーム形式が多くなることで、楽しさは保たれる反面、具体的な課題に向き合う時間が減り、成長が鈍化する可能性もあります。
4. とにかく量をこなせば強くなると思っている
「たくさんやれば上手くなる」という信念のもと、毎日ハードな練習を積み重ねることがあります。しかし、疲労によるパフォーマンス低下や、内容の質が落ちることで、むしろ逆効果になることもあります。無意識のうちに“練習をこなす”ことが目的になってしまう危険もはらんでいます。
5. 全員で同じ練習メニューをやる
部やチーム全体で一体感を出す、運営の効率化などの理由から、誰にとっても同じ内容をやらせることがあります。しかし、個人の課題は違うのにただ同じ練習メニューをこなすようにしては、成長が偏ってしまいがちです。もちろん、人数や環境の兼ね合いで同じ練習メニューをせざるを得ない状況はあると思いますが、その場合は個人個人が何にどう取り組むのかが明らかである必要があります。
6. 流行りのSNSや雑誌で見たものをそのまま入れる
「最近話題のトレーニング」や「バズっている方法」に飛びつきたくなる気持ちもわかります。ただ、背景や目的を理解せずに取り入れると、「なぜこれをやっているのか」を理解できず、形だけの練習になりがちです。
7. 自分の過去の経験に頼ってしまう
指導者がかつて選手だった頃の経験は、貴重な知見でもあります。ただ、その時の自分の置かれていた環境や課題、運動能力、思考の傾向は、今の選手とはまったく異なるかもしれません。自分にとって効果があった方法でも、それを他の選手にそのまま当てはめてもうまくいくとは限らないのです。
8. 試合に直結することだけをやる
「試合で使えることだけに絞る」という考えは、効率的に見える一方で、基礎や土台の力を育てる視点が抜け落ちることがあります。試合で現れた課題には、実はその裏にあるもっと根本的な要因が潜んでいることも少なくありません。そうした原因の原因に気づかないまま、表面的な練習を繰り返しても、その場しのぎの改善にとどまり、大きな成長にはつながりません。判断力や動きの精度が未熟なままゲームばかりをやっても、意図を持ったプレーが育ちにくくなるのと同じように、土台からの取り組みが不可欠です。
練習メニューとは、本来どういうものなのか
ここまで紹介したような練習メニューの組み方には、「練習に取り組めば上達していくはずだ」という前提があるのではないでしょうか。「自分」という存在に、「練習メニュー」というインプットをすることで、「できるようになった自分」というアウトプットがされるような、そんなイメージではないかと思います。けれど、本当はそうではないのではないでしょうか。
練習メニューとは、未完成の地図を歩きながら描いていくようなものなのではないでしょうか。
つまり、今の自分の立ち位置を確認するように自分に必要な課題と向き合い、前に進めているかを確認するように自分に変化が出ているかを観察し、時には歩く方向を変えたり少し戻るように練習メニューを調整するようにして、自分自身とメニューの両方に働きかけながら、未完成の地図を歩きながら成長への道筋を描いていくような行為です。それが、本質的な意味での「練習メニューに取り組む」ということではないでしょうか。
そのように取り組むメニュそして本来、メニューには楽しさや喜びが含まれているはずです。
- 昨日はできなかったことが今日はできたという手応え。
- 課題に向き合い、改善が見えたときの納得感。
こうした感覚は、「うまくなっていく道のり」を選手自身が実感できたときに自然と生まれます。そうしたプロセスになっているかどうかを確認しながら取り組むのが練習メニューなのではないでしょうか。
練習メニューは「成長の道のりをつくる道具」
では、どうすれば練習メニューをただの作業にせず、本当に成長につなげるものにできるのでしょうか?
1. 【課題を見つける】今つまずいているところをはっきりさせる
まずは、「いま、どこでうまくいっていないのか?」をはっきりさせましょう。
「今日はなんか調子が悪いな」「なにかうまくいかない」で終わらせずに、こんなふうに自分に聞いてみてください:
- どんな場面でうまくいっていない?
- 体の動き、判断、打ち方の何が原因か?
- うまくいっているときといっていないときで何が違ったか?
こうして具体的にすることで、「何を直せばいいか」が見えてきます。
2. 【練習メニューを考える】自分の課題に合わせた「作戦」を立てる
次に、「この問題を直すにはどんな練習がよさそうか?」という作戦(=仮説)を立ててみましょう。
たとえば:
- 前で打てない → 最初の一歩を早くする練習を入れてみる
- 判断が遅れる → 「見る→考える→動く」の順番を意識できる練習をしてみる
ただ、その練習で必ず変化が生まれるとは限りません。なぜなら考えた原因が、もしかしたら違うかもしれませんし、原因の原因があるかもしれません。そのため、「やってみて自分に変化があるかどうか」を確認しながら取り組むようにしましょう。
練習に取り組みながら、本当の原因を発見するためのスモールステップ練習についてはこちらも参考にしてください
👉️「できない」を「できる」に変える練習法
3. 【できたかを確認する】ちゃんと変わってる?を確かめ
練習メニューに取り組む中で、「できたか、できなかったか」を必ず確認しましょう。なんとなくで終わりにしないことが大事です。
- さっきよりできるようになってる?
- どんなポイントがうまくいった?
- なにがうまくいかなかった?
- うまくできたときとできないときで何が違う?
そして、もし「できたりできていなかったり」するとしたら、どのような時にできていないのか、それは何が原因か、できる回数を増やすためにどのような取り組みが必要か、を考え、工夫しながら取り組みましょう。
振り返りを的確に行うための視点の持ち方についてはこちらも参考にしてください
👉️結果を変える振り返りの技術
4. 【できないときはどうする?】観察と分解であせらず前に進む
もし「できていない」「できているかわからない」と感じたときには、練習メニューを簡単にしたうえで、「自分の動き・気づき・判断」を丁寧に観察しながら取り組みましょう。たとえば練習メニューを、ゆっくり取り組む、動きを小さくする、というかたちで、できるだけシンプルに、「できていない要素」が何かを発見できるように、その部分だけが搾り取れるように工夫した練習メニューは何かを探しながら、取り組んでみましょう。
そのうえで、
- どの動きがうまくいっていない?
- 自分の意識はどこを向いている?
- 体のどこに力が入ってる?
といった問いかけをしながら、取り組んでみましょう。
たとえば、「タイミングが合わない」なら「準備が遅い?」「相手を見るのが遅い?」「足が止まってる?」など、原因を細かく探すことで、次に試すヒントが見つかります。
焦らなくて大丈夫です。勝負の場面とは、実は本当にわずかな動きや瞬間の積み重ねで決められています。原因を掘り下げていくことは、勝負を決する直接的な要因には結びつかないように思われるかもしれませんが、実は本当の原因に近づいています。ひとつずつ超えていきましょう。
観察について細かく解説した内容はこちらもご覧ください。
👉️観察で努力と結果が変わる。観察からはじまる上達の循環
5. 【自分の地図を描く】どんなふうに成長しているかを覚えておく
こうして、「課題を見つける→練習してみる→できたかを確認→調整する」ことを繰り返していくと、だんだん自分の成長ルートが見えてきます。
たとえば:
- こういう練習をしたら、こう変わった
- このときはここがブレーキになってた
- こんな工夫をしたらうまくいった
この「自分だけの道のり」を覚えておけば、次に壁にぶつかったときにも、きっとヒントになります。
また、時には、今の取り組みが目標につながっているかどうか不安になるときや、あるいは少しこだわりすぎてしまって本当は他の原因に取り組んだほうが良いときもあるかもしれません。自分が今どう取り組み、それが何のため、どうつながっているのかを考えながら取り組むことで、正しい方向に歩むことができます。
最後に:練習メニューは「自分を変えるための作戦」
練習メニューは、「やればできるようになる」と信じてただこなすだけのものではありません。実際には、どんな課題があって、それに対してどう取り組み、何が変化したのかを観察しながら、少しずつ進めていく必要があります。そうやって自分の状態に合わせて調整したときに、はじめて練習メニューは本当の意味で“自分を変える道具”になります。
「今の自分にとって必要なことはなにか?」「少しでも変化が出ているか?」を考えながら、試したり、観察したり、やり方を変えたりしながら、自分と向き合って練習メニューに取り組むことが、あなたの成長の力になります。
