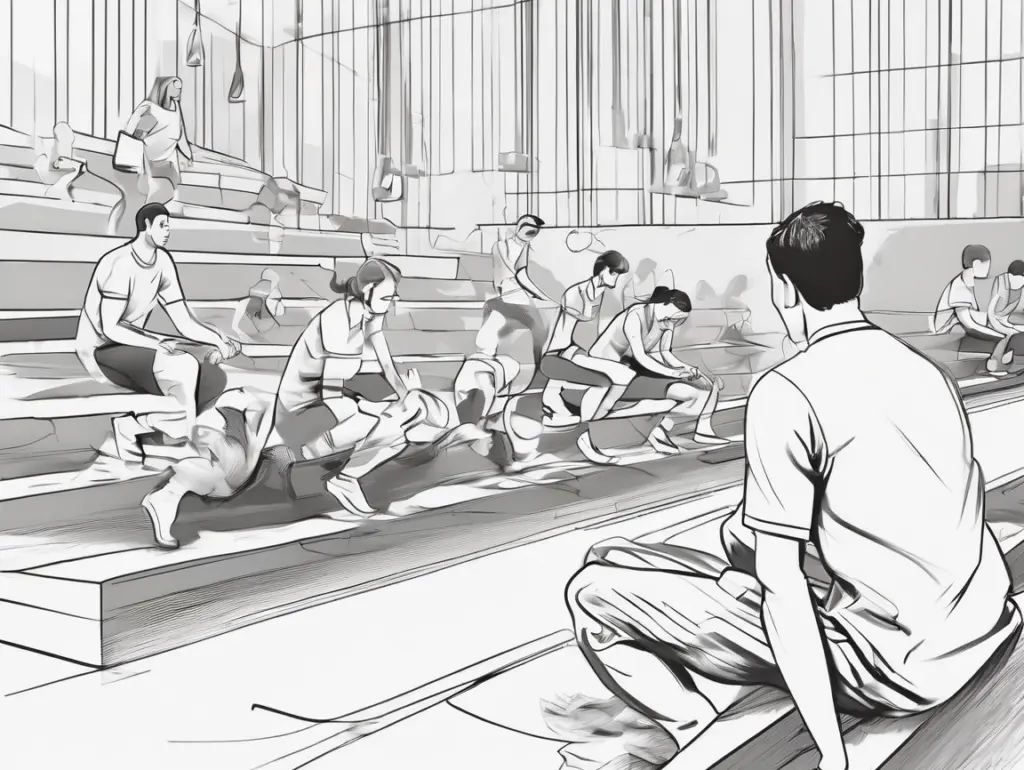
練習とは、身体や認知のプログラムを修正し、少しずつ更新していく作業です。その際に役立つのが「スモールステップ」の考え方です。大きな課題を一気に解決しようとするのではなく、小さな段階に分けて進めることで、確実に前進することができます。スポーツにはたくさんの要素が関係します。焦って早く結果を出そうとするほど、練習の意図や変化があいまいになり、自信も積み上げることができません。小さな単位で変化を観察し、それを積み上げることが、遠回りに見えて最短距離のアプローチになります。
目的設定(準備)
最初にすべきは「課題を明確にすること」ですが、実際には本当の課題や原因を明確にすることは難しい場合や、最初からなかなか見つからない場合もあります。「なんとなく不安定」「うまくいかない感じがある」──そうした曖昧な感覚からスタートすることも自然です。
そこでまずは、「仮のテーマ」で構いませんので、今の自分の課題の原因と思われるものを設定してみましょう。重要なのは、そのテーマで一度取り組み、試す中で、「何が違ったか」「何が手がかりになりそうか」を掴んでいくことです。
そして、練習後に振り返ることで、最初に考えた原因が合っているのか、もしくは原因の原因があるのか考えてみましょう。原因が異なっていれば修正し、徐々に焦点を絞っていくプロセスが、スモールステップでの練習設計になります。
スモールステップ実践のプロセス
目的設定で考えた原因に基づいて実際に取り組んでみる中で、それが本当の原因なのか、あるいは他の原因があるのか、このまま練習をしてよいのかどうか、を考えながら取り組んでみましょう。
ここで重要なのが、次の3つの視点で練習結果をチェックすることが、効果的に進めるポイントになります:
- 意識して取り組めているか
- 意識した原因が変化しているか
- 原因が変化しているときに、結果が変わっているか
たとえば、「打点が遅れる」という課題に対して「振り出しが遅い」という原因があると考えてみましょう。取り組みを実践するときには、振り出しを早くする意識ができていたか、そして振り出しを早くする意識ができたときに実際に振り出しが早くなっていたか、振り出しを早くできていたときに打点が遅れずに打てていたか、を確認してみます。
たとえば、原因があいまいや漠然としたまま意識をしても、実際には行動が変化しない場合があります。たとえば「膝を使おう」「しっかり構えよう」「足を動かそう」と意識していても具体的でないのでと体はどう変化を起こしてよいのかわかりません。
また、もし取り組みをして変化が起きたとしても、設定した原因が実はズレていた場合、本来変えたかった結果にはつながらないこともあります。たとえば、「打点が遅れる」のは「振り出しが遅い」のではなく、「構えが遅れている」「ボールへの入り方が浅い」など他の要因だった場合、振り出しの改善では結果が変わらないことになります。
だからこそ、「原因が意識できたか」「意識した原因が変化したか」「原因が変化したときに結果が変わっていたか」を明確に追っていく必要があります。
観察 → 再設計
練習取り組みながら確認した、3つのチェックポイント(意識して取り組めているか、取り組んだ内容が実際に変化しているか、その変化が結果につながっているか)を観察し、練習を再設計します。
- 意識して取り組めていない場合:そもそも意識する内容が抽象的すぎる、意識する余裕がない、注意が分散している、などの理由が考えられます。この場合は練習メニューと取り組む内容があっていない場合があります。「一つだけ意識する」「動作をシンプルにする」「ゆっくりした状況で始める」など、意識しやすい条件を整えましょう。
- 取り組んだ内容が変化していない場合:意識はできていても身体が変化していない時は、「どこをどう変えるか」が明確になっていない、あるいは練習内容と取り組み内容が合っていない可能性があります。原因の、さらなる原因がないかどうか、動きや時間をさらに細かく分解したり、原因を生み出す前の時間帯に注目して、自分が変化を起こすことができる原因を考えてみましょう。また、たとえば体の動きを変えようとするのに、実戦に近い練習をしても変化は起こせません。できるだけ単純な動きや素振り等から実践することが正しい道のりです。意識していても変化が見られない場合は、練習内容が、原因に集中して取り組むことができるものか、確認してみましょう。
- 変化が起きても結果につながっていない場合:そもそも設定した原因が違っていたか、複数の要因が絡んでいるかもしれません。結果と結びつかない場合は、原因の再検討や別の要因がある可能性を考えてみましょう。
これらの振り返りに基づいて新しく設定した「原因」に取り組めるように練習を再度考えてみましょう。このように、目的設定→実践→観察→再設計というループが、スモールステップ練習の本質です。練習を通して見えてくる「できている/できていない」は、そのまま次の段階設計の素材になります。このループを繰り返す中で、課題はより具体的になり、スモールステップはより確かな足場になります。
定着化
一度できたからといって、それが「身についた」とは限りません。試合では練習以上に複雑な要素が絡み、意識は外へ向きます。その中であっても自然と再現できるレベルまで持っていくことが、本当の定着です。
定着させるには、繰り返しでの反復練習で体の中のプログラムを自動的になるようにすることと同時に、実戦でも使えるプログラムにすることが重要です。
実戦では、試合の流れ、相手の状況、自分の状況、強み弱み、といった様々な要素を考えながら戦う必要があります。そのため、できる限りのことは、考えずに自動的に反応できるようにしておくことで、本来集中すべきことに意識を向けることができます。そのために、ある程度できるようになってもそこで良しとせず、「意識せずともできる」ところまでできるようにすることが必要になります。
さらに重要なのは、ただ「できる」だけでなく、それを実戦で使えるレベルに引き上げていくことが重要で、そのためには、練習と試合の間に段階を設けて練習を積み重ねる必要があります。
「意識せずともできる」ようになったら、実戦に近い状況での練習、プレッシャーのある中で同じ動作を繰り返す、相手の動きに応じて判断する場面を作るなど、段階的に環境を複雑にしていきましょう。たとえば、連続で成功させる練習や勝敗やプレッシャーのかかる条件設定をした練習を考えます。これにより、試合で使えるものになります。もしこのステップを飛ばしてしまうと、練習ではできていても、試合では動けない、再現できないという事態が生じます。「できるようになったのに勝てない」「練習では上手くいっていたのに試合では崩れる」といった現象は、このステップが不足していることが大きな要因です。
ケース対応と注意点
できない/わからない
スモールステップで組んだ練習でも、うまくいかないとき、わからないときが出てきます。そのようなときは、まずは自分の観察することが出発点になります。
特に、できているときとできていないとき、良いときと悪いときを比べることで、原因を探し当てるヒントが得られます。もちろん原因を探すヒントとしてアドバイスや知識を取り入れるのも一つの方法ですが、それが本当に自分の原因かどうかは確かめなければなりません。実際には複数の原因が絡んでいる課題に対して、自分にとっての本当の原因とは異なる取り組みをしてしまうことになり、取り組んでいるのにいっこうに改善しない、ということが起きてしまいます。
だからこそ、自分で考え、試した内容が改善しているかどうか、良いときと悪いときで何が違うかを観察することで、原因を探し出すことができます。
また、観察をしてもわからない場合には、動きをゆっくりにしたり、練習をもっと簡単にして取り組むことで、原因を見つけやすくなります。
観察をし、必要に応じて課題を小さく分けたり条件を簡単にすることで、「ここまではできている」「ここからができていない」と境界が明確になります。これによって自分に合った原因が浮かび上がり、次の練習を具体的に設計できるようになります。複雑な原因を丁寧にほぐしていくことで、新しい一歩の設計が見えてきます。
小さく改善を重ねる
変化を焦るあまり、いきなり大きな修正をしようとすると、逆に感覚を失ってしまうことがあります。昨日より少し良くなる、小さく工夫してみる、その積み重ねが、自信のある動作や判断に育っていきます。
とはいえ、スモールステップに取り組んでいると、「ゴールまで遠い」「こんなに時間がかかっていて大丈夫か」といった焦りが生じることも少なくありません。しかし、焦って大きな変化を求めると、結局はどこが変わったのか、何が有効だったのかがわからなくなり、再現性も失われてしまいます。
全体像を見ながら、「今はここに取り組んでいる」と思う視点は大切ですが、実際の練習では一つひとつを丁寧に積み重ねることが、結果として一番早くゴールにたどり着く方法になります。
ただ一つの課題をとってもスポーツには多くの要素があります。「打点を安定させたい」という目標があったとしても、そこに直接アプローチしようとせず、「打点までの入り方」「構えの時間」「判断の早さ」など、要素に分解してそれぞれを少しずつ整えていくことが、結果的に安定した打点を実現する近道になります。
小さく区切るからこそ、変化に気づきやすくなり、自信を持って次のステップに進むことができます。そして、その確かな足場の積み重ねこそが、大きな変化を生み出す力になります。
まとめ
スモールステップは、単に練習を細かく分ける方法ではなく、成長のプロセスを明らかにするための枠組みです。課題がうまく改善できないとき、小さく区切ることで変化を観察でき、できていることとできていないことの境界が見えてきます。そこから本当の原因を探し出すことが可能になります。スモールステップは、上達を偶然に任せず、必然に変えるための仕組みなのです。
「スモールステップ練習で“できる”を増やしていくことは大切ですが、それでも“ミスをしない自分”という前提が強いと、焦りや崩れが起きやすくなります。本記事では、ミスそのものを観察し、想定し、再現練習へとつなげる“崩れにくい構造づくり”を解説しています。
👉️ミスを引きずる人と切り替えられる人の小さな違い
動きだけでなく、緊張やメンタルに対してもスモールステップでの練習設計は有効です。試合での緊張を練習で取り入れる考え方についてはこちらも参考にしてください。
👉️“ここぞの場面”で落ち着ける人の頭の中
